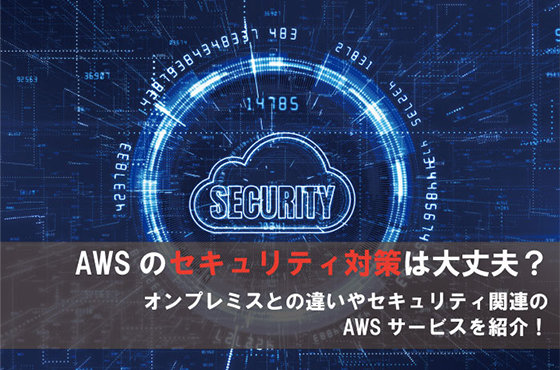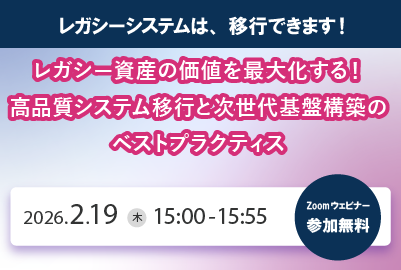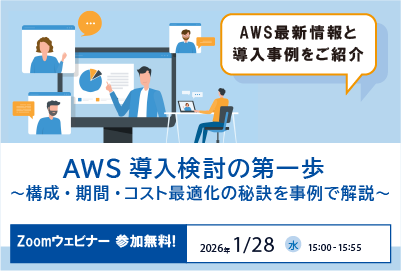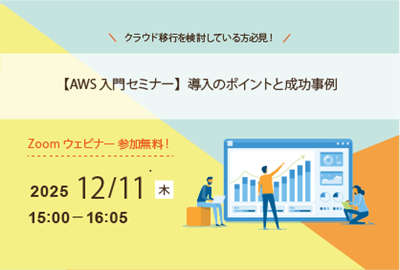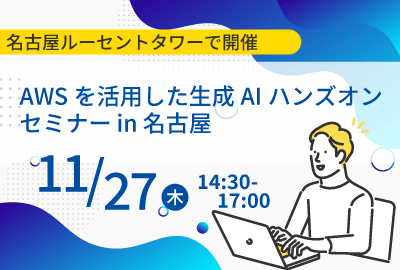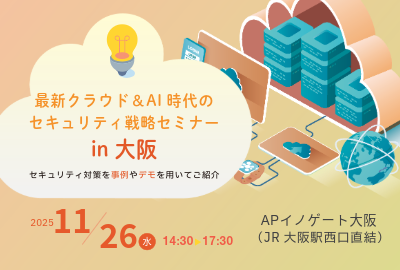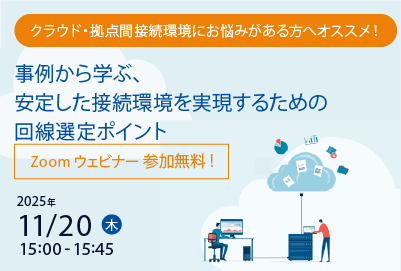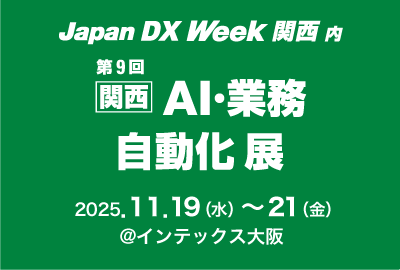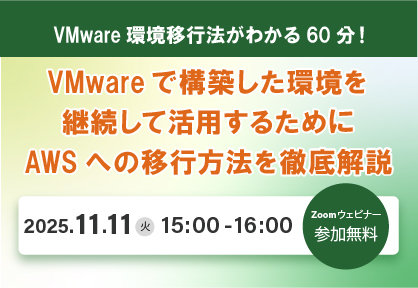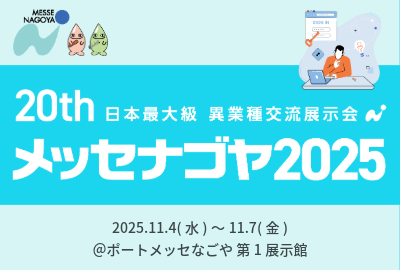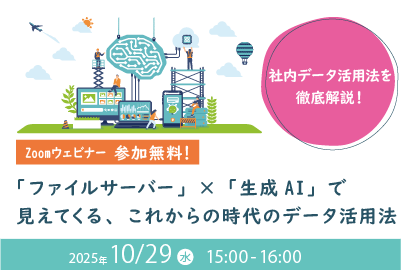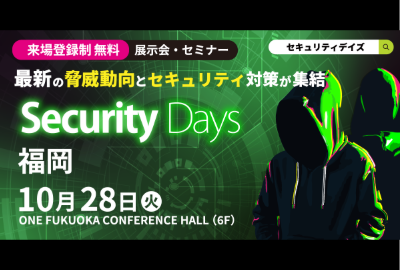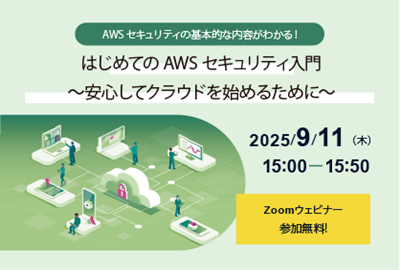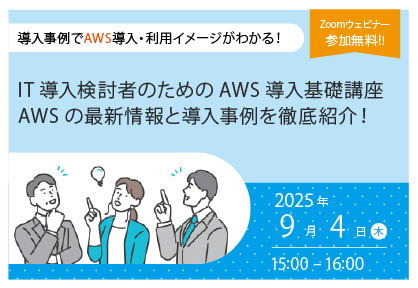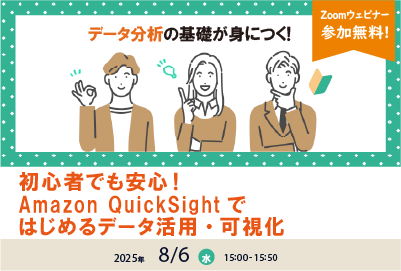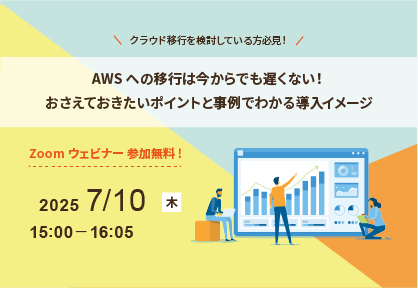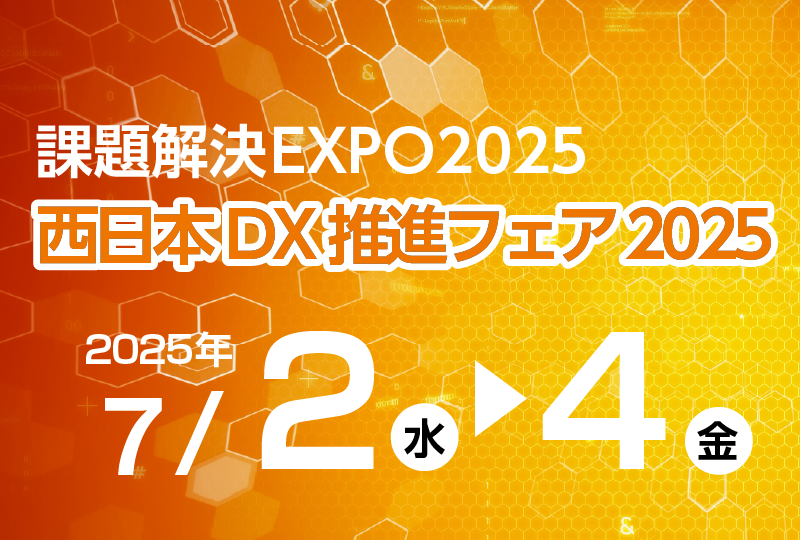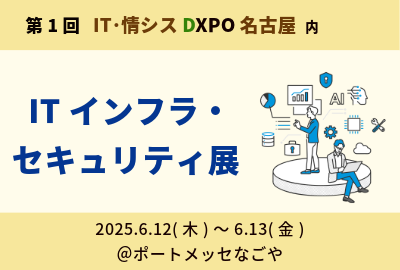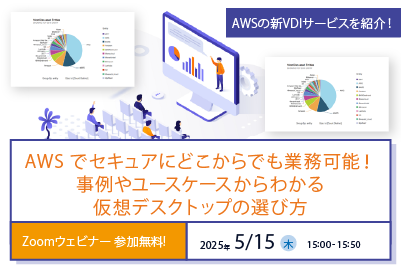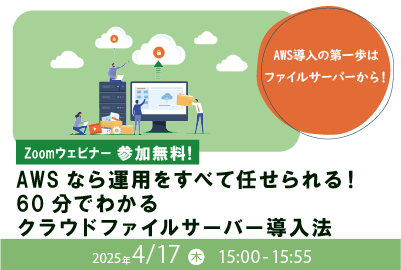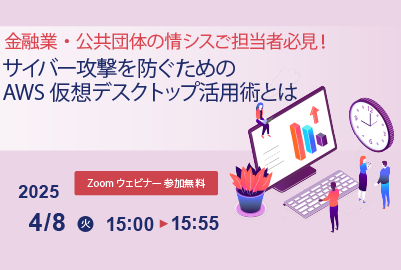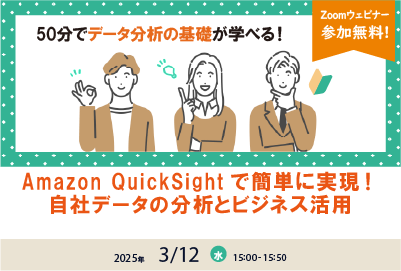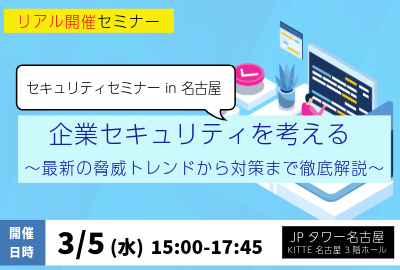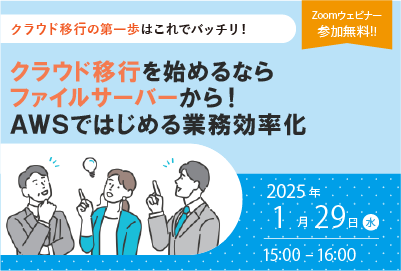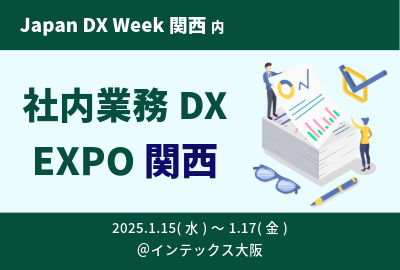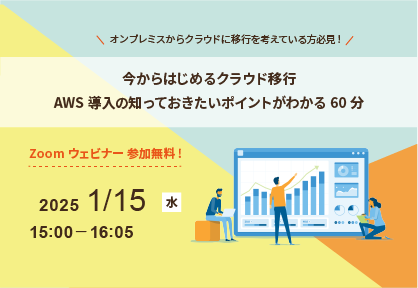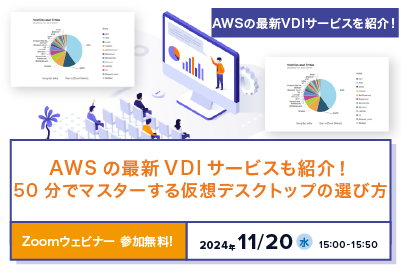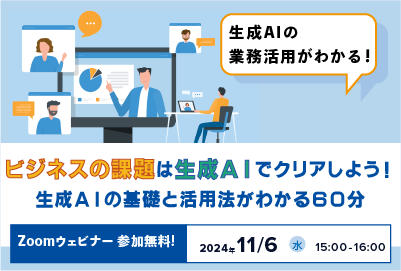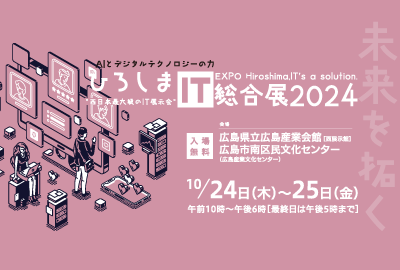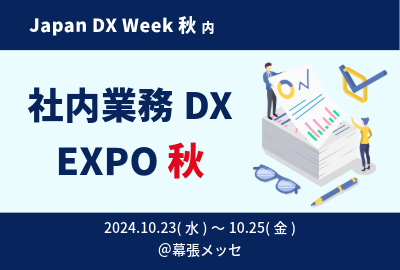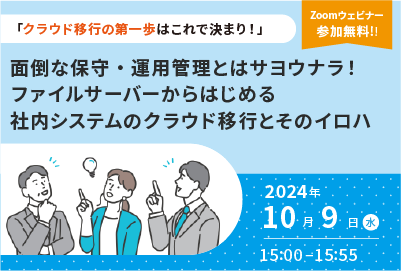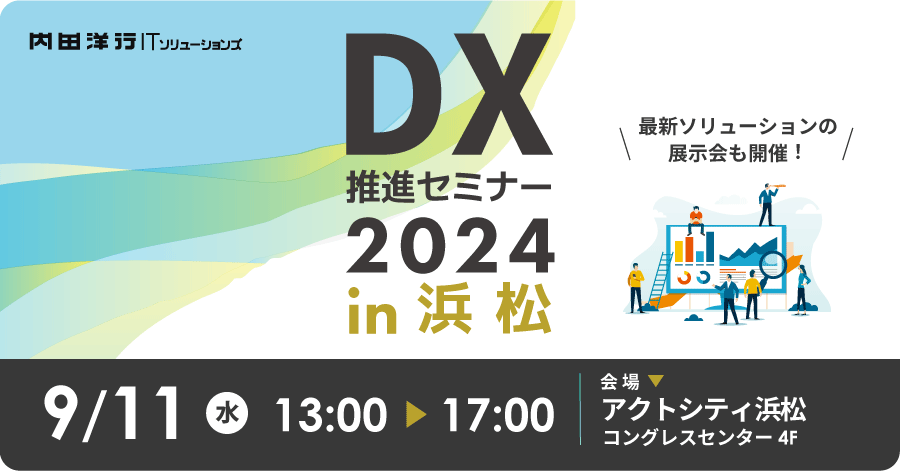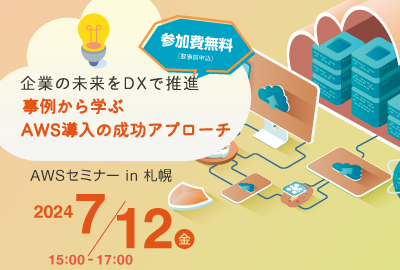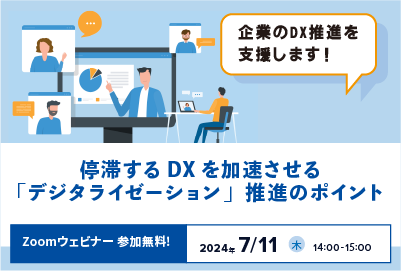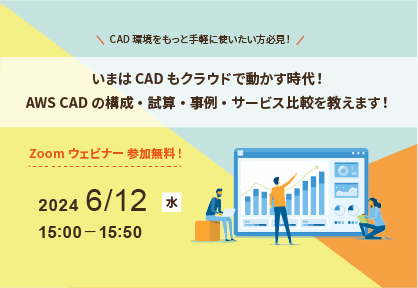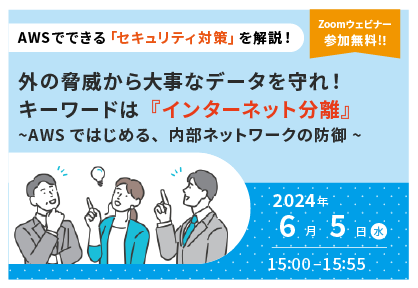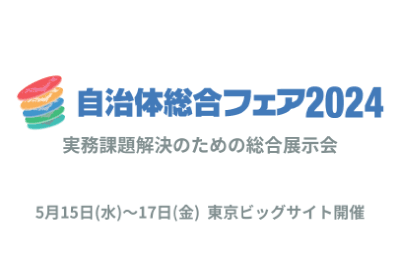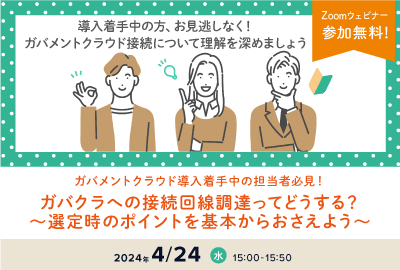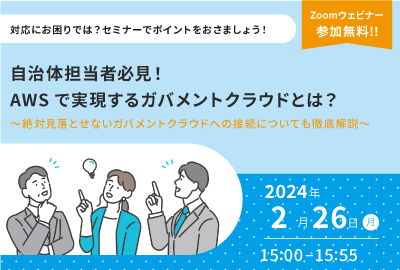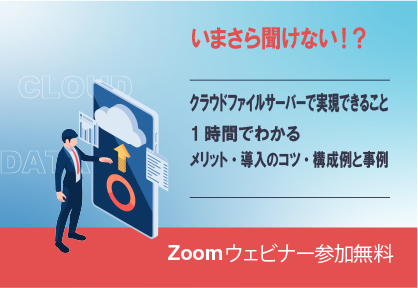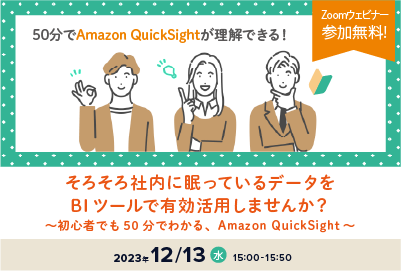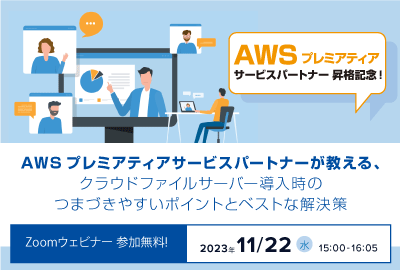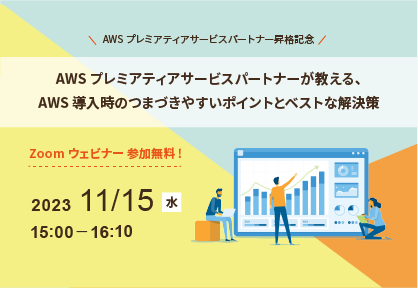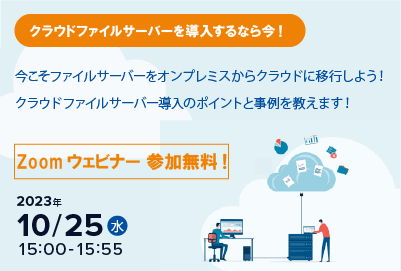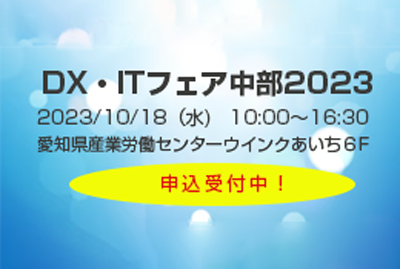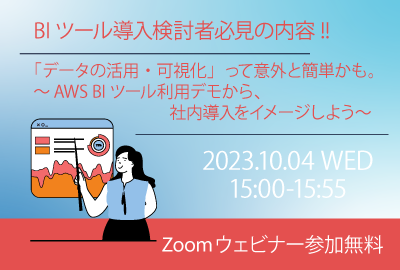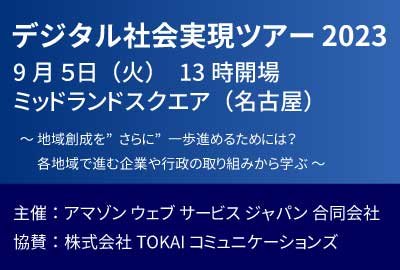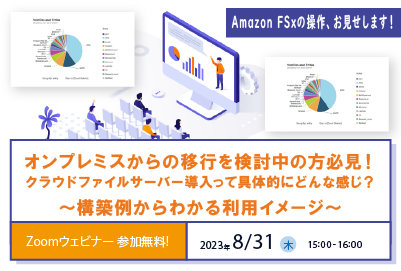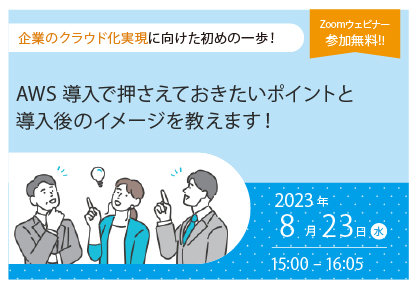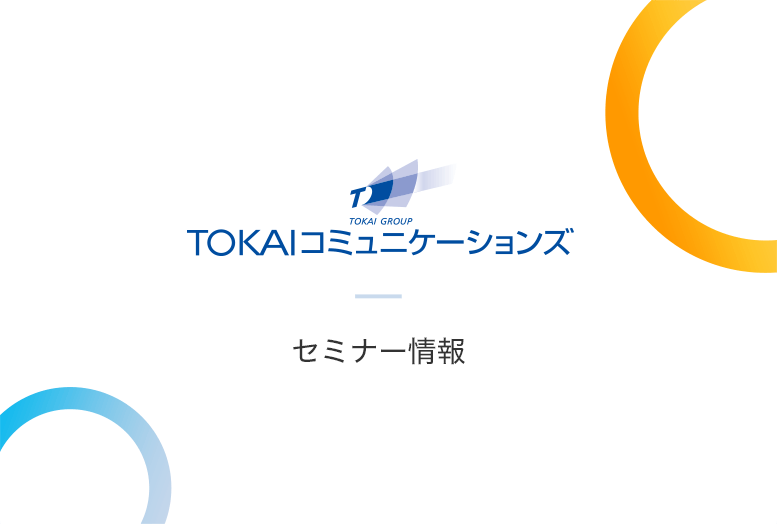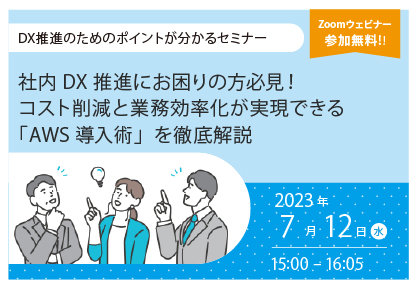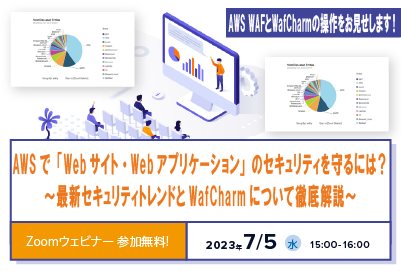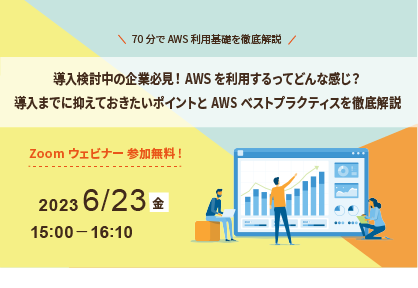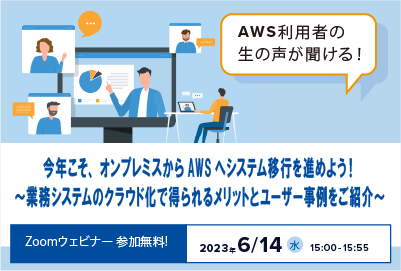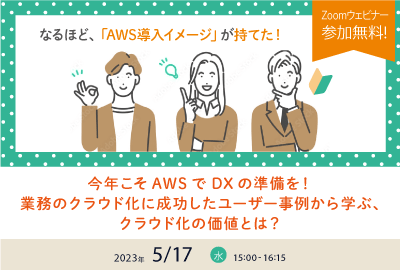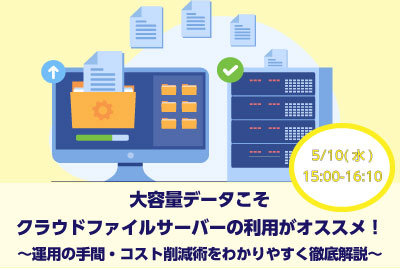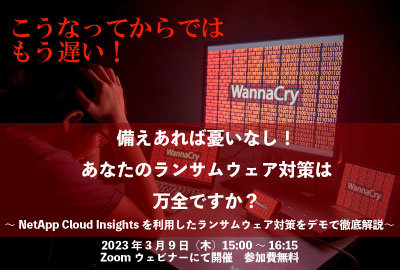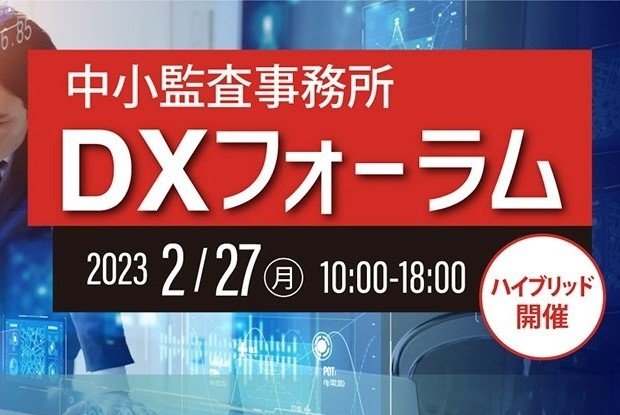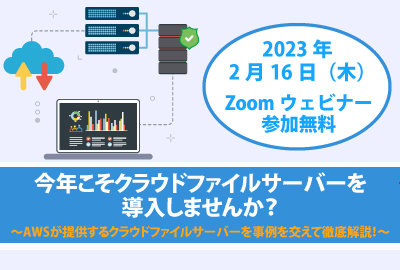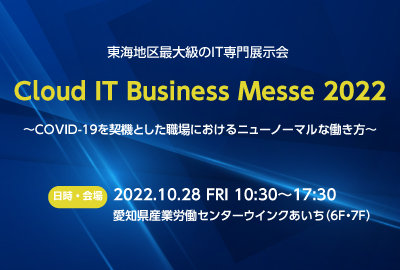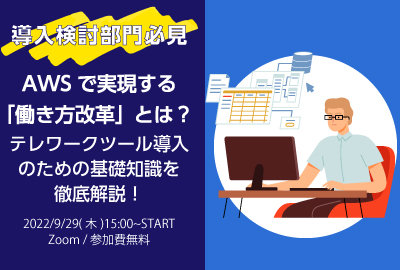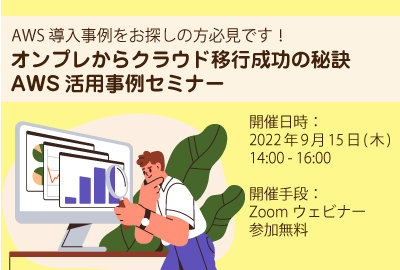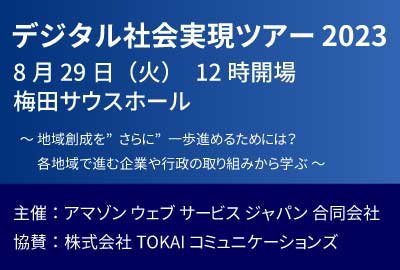AWS(Amazon Web Services)をこれから学びたい、試してみたいという方にとって、「無料利用枠」はありがたい仕組みです。
Amazon EC2やAmazon S3、Amazon RDSといった主要サービスを、一定の条件下で無料で利用できるこの制度を正しく理解すれば、開発・検証・学習目的での導入コストを大きく抑えることが可能です。
しかし、無料といえども利用条件を把握していなければ、思わぬ課金が発生するリスクもあります。本記事では、AWS無料利用枠の種類や仕組みを解説しつつ、主要サービスごとの無料範囲や注意点をわかりやすく整理して紹介します。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
目次
AWS無料利用枠とは何か?
ここでは、AWS無料枠の概要について解説します。
無料利用枠の種類と概要(12ヶ月/無期限/トライアル)
AWSの無料利用枠は大きく分けて「12ヶ月限定の無料枠」「無期限で使える常時無料枠」「サービスごとに異なる短期トライアル枠」の3種類に分類されます。
それぞれの特徴と、対象となる主なサービス、さらに利用中のプランによって異なる注意点を以下の表に整理しました。
無料利用枠の種類別対応表
| 無料枠の種類 | 利用可能期間 | 対象サービス例 | 利用条件・注意点 |
|---|---|---|---|
| 12ヶ月無料枠 | AWSアカウント作成から12ヶ月間 | - Amazon EC2(t2.micro / t3.micro) - Amazon RDS(MySQL / PostgreSQL) - Amazon S3(5GB)など |
利用可能時間やストレージ容量に制限あり。期間満了後は自動で課金開始。 インスタンスタイプの選定やリージョン設定に注意が必要。 |
| 常時無料枠(無期限) | 無期限 | - AWS Lambda(100万リクエスト/月) - Amazon DynamoDB(25GB) - Amazon CloudWatch(基本機能)など |
上限を超過した場合は即時課金。機能追加オプション利用時も料金発生。 |
| 短期トライアル枠 | サービスによって異なる(例:30日など) | - Amazon CloudWatch Logs(5GB) - Amazon Macieなどの新規または限定的なサービス |
新規サービスや一部機能のプロモーション目的。トライアル終了後は自動で有料に切り替わる。対象の明示がないサービスもある。 |
例えば、Amazon EC2を無料で使用するには、無料枠に指定されたインスタンスタイプ(t2.microまたはt3.micro)を1ヶ月750時間以内で稼働させる必要があります。複数起動や別タイプ選択により無料枠を超過すると、即時に課金が始まります。
また、Amazon DynamoDBなど常時無料枠のサービスもありますが、上限を超えると課金対象となるため、「無制限に無料」という認識ではなく、あくまで条件付きであることを忘れないようにしましょう。
なぜ無料枠の理解が重要なのか?
AWSの無料枠は有用ですが、仕組みを理解しないまま利用すると、意図せず料金が発生するリスクがあります。
特に注意すべきなのは、「無料枠=全てが無料」ではないという点です。例えば、Amazon EC2の無料利用枠は750時間/月と定められていますが、2台以上のインスタンスを同時に稼働させたり、使用を停止し忘れて24時間稼働が続いたりすると、すぐに上限を超えてしまいます。
Amazon S3でも、ストレージ容量5GBまでは無料となっていますが、PUTリクエスト2,000回、GETリクエスト20,000回といったリクエスト数にも制限があります。動画や画像を頻繁にやり取りする構成では、この回数制限に早期到達することも少なくありません。
加えて、リージョンによって無料枠が適用されないケースもあるため、東京リージョンなど国内でよく使われる地域が対象かどうかの確認も重要です。
無料枠という言葉に安心せず、サービスごとの利用条件や制限値、対象リージョンなどを把握した上で活用することが、AWSを安全かつ効果的に使いこなすための基本です。
主要サービスごとのAWS無料枠まとめ
AWS無料利用枠の活用は、単に費用を抑えるだけでなく、実際のサービスに触れながら学習・検証環境を構築できる点でも大きなメリットがあります。ここでは、代表的なサービスごとに、無料枠の内容や注意点を詳しく解説します。
Amazon EC2(仮想サーバー)
Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)は、仮想サーバーを手軽に構築・運用できる代表的なサービスです。無料利用枠では、t2.microまたはt3.microインスタンスが1ヶ月あたり750時間まで無料で利用可能となっています。
ただし、750時間というのは「インスタンス1台を1ヶ月間フル稼働させる」場合に相当する時間です。例えば、同時に2台のインスタンスを立ち上げると、1台分は超過扱いとなり、即座に課金が発生します。
また、無料枠が適用されるのは特定のリージョンおよび特定インスタンスタイプに限定されるため、インスタンス作成時に対象外の構成を選択しないよう注意が必要です。開発・検証・学習環境の構築には適していますが、本番運用や高負荷処理には向きません。
Amazon S3(ストレージサービス)
Amazon S3(Simple Storage Service)は、オブジェクトストレージとして静的ファイルの保存やバックアップなどに活用されるサービスです。無料枠では以下の利用が可能です。
- ストレージ容量:5GB
- PUTリクエスト:2,000件/月
- GETリクエスト:20,000件/月
この枠内であれば、静的ウェブサイトのホスティングやファイル保管、API経由でのデータ受け渡しなどが可能です。しかし、画像や動画などファイルサイズの大きなデータをアップロードするとすぐに容量を使い切ってしまうため注意しなければなりません。
また、リクエスト回数も見落とされがちな課金要因です。アクセスの多いファイルに対するリクエストが積み重なると、上限を超えた分が自動的に課金対象となるため、Amazon CloudFrontとの併用やキャッシュ設定による工夫も検討しましょう。
Amazon RDS(リレーショナルDB)
Amazon RDS(Relational Database Service)は、MySQLやPostgreSQLなどのリレーショナルデータベースをマネージド環境で提供するサービスです。無料利用枠では、以下のリソースが対象となります。
- データベース稼働時間:750時間/月
- 汎用ストレージ:最大20GB
- バックアップストレージ:最大20GB
Amazon EC2と同様に、「750時間/月」という上限は1インスタンス分に相当します。複数インスタンスの同時稼働や稼働停止の忘れが原因で上限を超えるケースもあるため、運用管理には注意が必要です。
無料枠は、アプリケーションの開発やテスト用途に最適であり、本番稼働を想定したパフォーマンステストを実施するにも十分なスペックが確保されています。
なお、無料対象となるのはMySQLとPostgreSQL(およびMariaDB)であり、OracleやSQL Serverの利用には別途ライセンス費用がかかります。
その他の無料枠対応サービス
AWSには、12ヶ月限定枠やトライアル枠とは異なり、常時無料で使えるサービスも複数存在します。代表的なものは以下のとおりです。
- AWS Lambda:100万リクエスト/月、400,000GB-秒
- Amazon DynamoDB:最大25GBのストレージ
- Amazon CloudWatch:10個のカスタムメトリクス+5GBログストレージ
- AWS Glue Data Catalog:1,000テーブル、1百万オブジェクトまで無料
- Amazon SNS/Amazon SQS:1百万メッセージまで無料
これらの常時無料サービスは、インフラ構築だけでなく、サーバーレスアーキテクチャの学習や軽量アプリケーションの構築に役立ちます。
例えば、AWS LambdaとAmazon API Gatewayを組み合わせれば、完全無料でREST APIを構築することも可能です。Amazon DynamoDBと連携すれば、データベースを含めたフルスタック開発も無料枠内で実現できます。
ただし、サービス間の連携や外部からのリクエスト処理などにより、無料枠の対象外リソースが発生する可能性もあるため、構成全体を俯瞰した上での設計が重要です。
AWS無料枠を安全に活用するための注意点
AWSの無料利用枠は便利ですが、使い方を誤ると思わぬ課金が発生するリスクがあります。ここでは、無料枠を活用する上で見落とされがちな注意点を以下の3つの視点から整理します。
- 無料枠を超えると自動課金される仕組みに注意する
- 利用リージョンやサービスの対象範囲を必ず確認する
- 利用状況の確認とアラート設定で課金リスクを防止する
無料枠を超えると自動課金される仕組みに注意する
AWSの無料利用枠には、各サービスごとに「時間」「容量」「リクエスト回数」などの上限が設けられており、その上限を超過した分は即座に課金対象となります。
例えば、Amazon EC2の場合は、無料枠として提供される750時間/月のインスタンス利用時間を超えた時点で、超過分に対して時間単位での課金が発生します。複数インスタンスを起動していたり、t3.mediumなど対象外のインスタンスタイプを使っていた場合も同様です。
また、Amazon S3においては、ストレージ使用量(5GB)やGET/PUTリクエスト数の制限を超えると、データ転送量やリクエスト単位で課金が積み重なっていきます。大量の静的ファイルをアップロード・配信している場合は、気づかないうちに課金対象になっているケースが多く見られます。
「無料だから」と油断せず、毎月の上限値を意識して構成・運用することがコストトラブル回避の第一歩です。
利用リージョンやサービスの対象範囲を必ず確認する
AWSの無料利用枠はすべてのリージョンやすべてのサービスに自動で適用されるわけではありません。リージョンによっては、無料枠が対象外だったり、提供条件が異なっていたりするため注意が必要です。
例えば、Amazon EC2で無料枠を利用できるのは「t2.micro」「t3.micro」インスタンスですが、一部のリージョンではこれらのインスタンスがサポートされていなかったり、無料枠適用外だったりします。誤って該当しないリージョンでインスタンスを立てた場合、起動した時点から料金が発生します。
また、Amazon RDSでは、MySQLやPostgreSQLが無料対象となりますが、OracleやMicrosoft SQL Serverは無料枠の対象外であり、ライセンス料金が別途加算される点にも注意が必要です。
サービス利用前には、AWS公式の無料枠対象条件ページやリージョン対応表を確認しておくことをおすすめします。
利用状況の確認とアラート設定で課金リスクを防止する
無料枠を安全に活用するためには、「今どのくらい使っているのか」を可視化し、異常があれば即座に気づける仕組みを整えておくことが欠かせません。
そのために活用したいのが以下の2つの機能です。
- AWS Budgets:無料枠の使用状況やコストの上限を設定でき、しきい値を超えた際にメール通知などでアラートを受け取れます。
- Amazon CloudWatch:インスタンスの稼働状況やリソース使用量をモニタリングし、異常な使用を検知して自動通知することが可能です。
例えば、Amazon EC2を常時稼働させたつもりがなかったのに、停止し忘れて課金されていたというケースも、Amazon CloudWatchのアラートで早期発見できます。
AWSはユーザー自身で管理しない限り、使った分だけ自動で請求されるという設計です。したがって、無料枠を超える前に気づくための監視・通知体制は必ず導入しておきましょう。
まとめ
AWS(Amazon Web Services)の無料利用枠を正しく理解し、うまく活用すれば、初期費用をかけずにクラウド環境を構築・試用することが可能です。
Amazon EC2・Amazon S3・Amazon RDSをはじめとする主要サービスには、それぞれ無料枠の制限が設定されていますが、その枠内であれば本格的な開発・検証・学習用途にも十分対応できる内容となっています。
一方で、無料枠といっても上限を超えれば即課金が発生するため、対象サービス・インスタンスの種類・リージョン・使用量の確認など、運用におけるリスク管理も不可欠です。 AWS BudgetsやAmazon CloudWatchなどを組み合わせることで、コストの可視化と通知による制御も実現できます。
AWS導入や構築、移行、運用でお悩みの方は、TOKAIコミュニケーションズへお気軽にご相談 ください。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
関連サービス
おすすめ記事
-
2024.08.28
セキュリティ・バイ・デザイン入門|AWSで実現するセキュリティ・バイ・デザイン
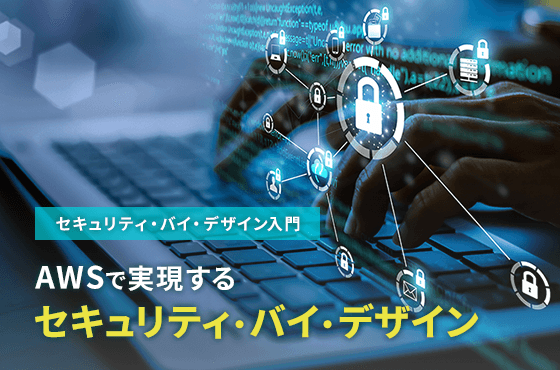
-
2024.04.10
AWSを使って障害に強い環境を構築するポイント(システム監視編)
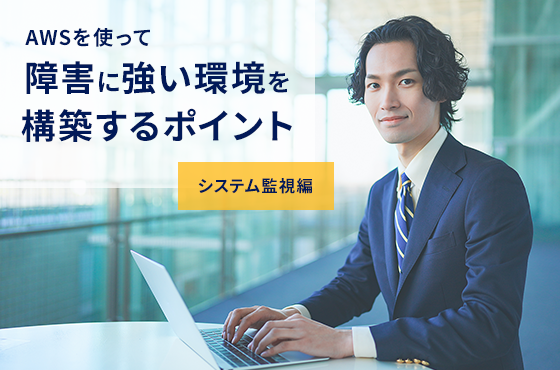
-
2023.07.04
クラウド利用時に知っておくべきセキュリティ知識【基礎編】

-
2023.06.15
AWSでゼロトラストセキュリティを実現する方法や、メリットをわかりやすく解説!

-
2023.06.05
AWSのセキュリティ対策は大丈夫? オンプレミスとの違いやセキュリティ関連のAWSサービスを紹介!