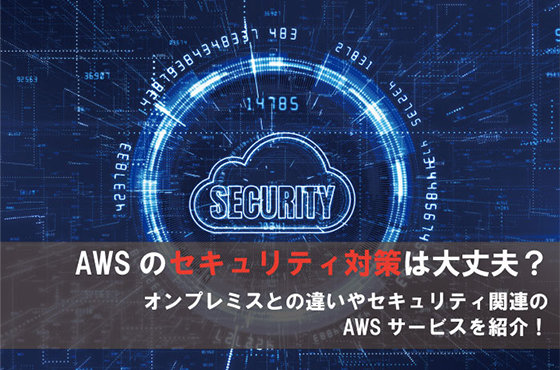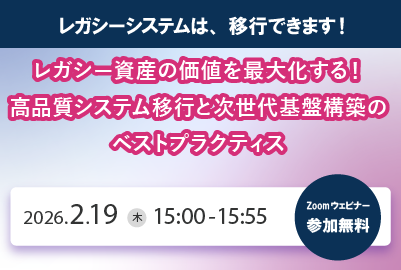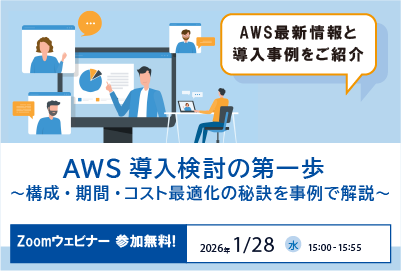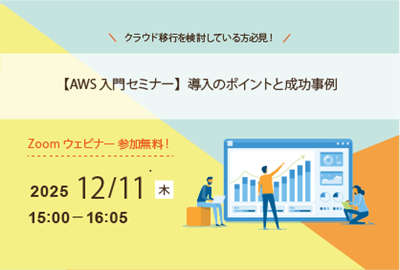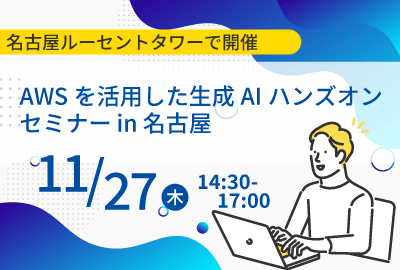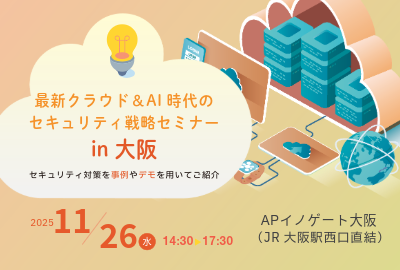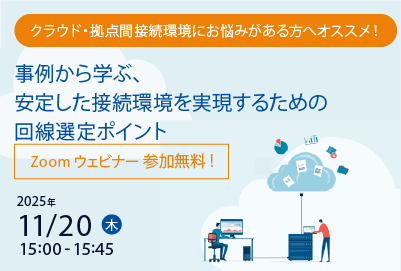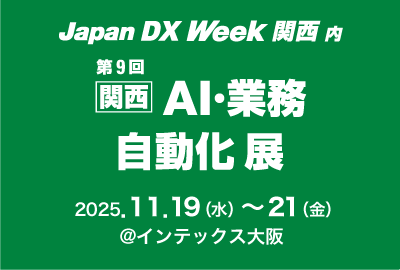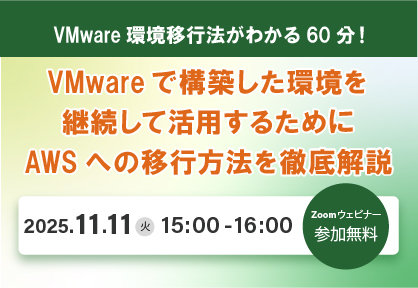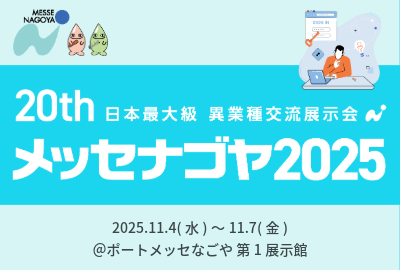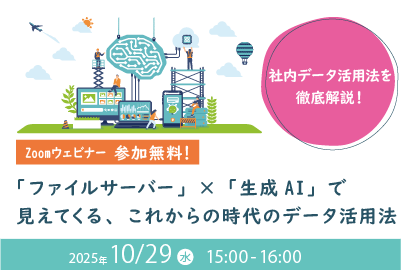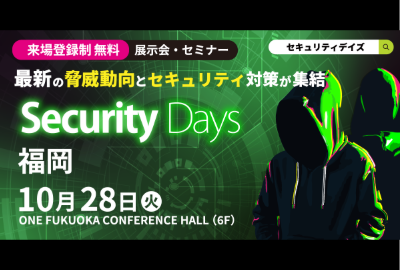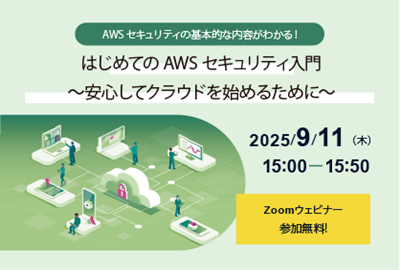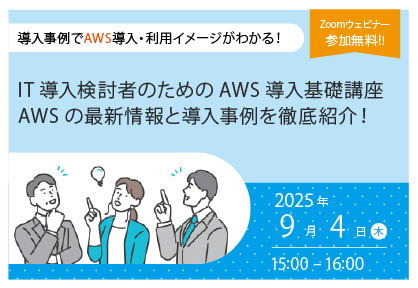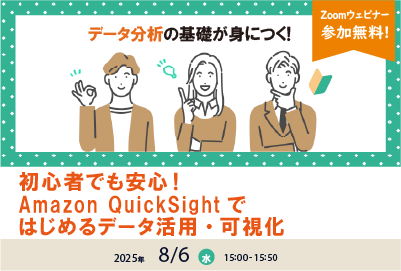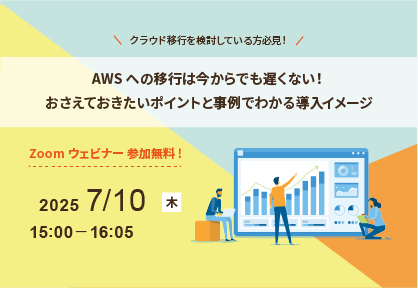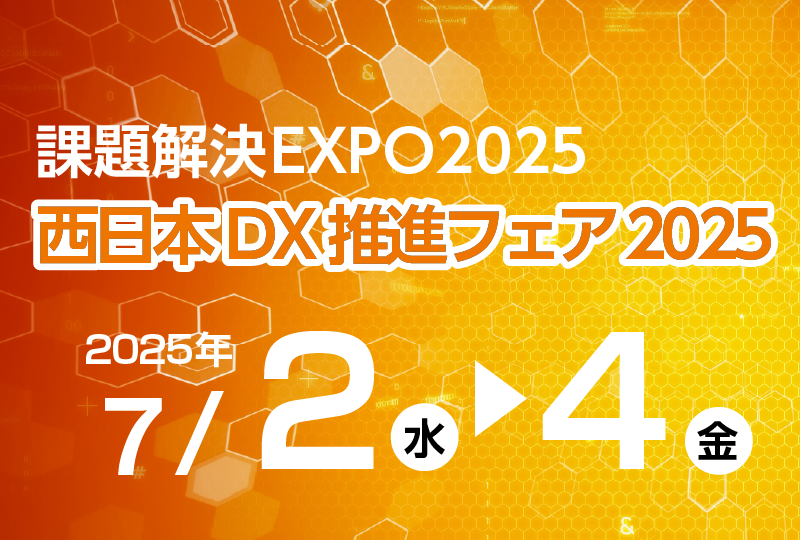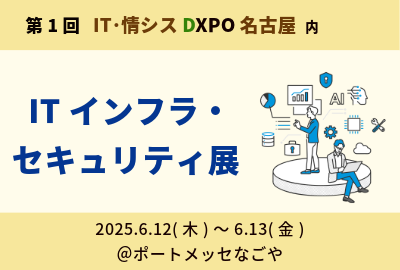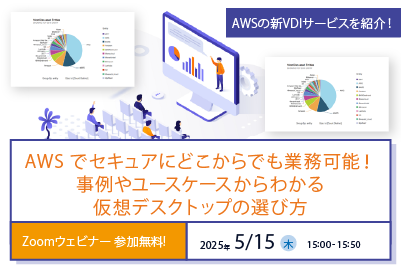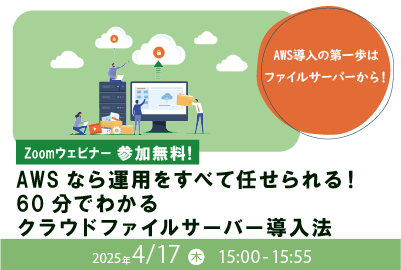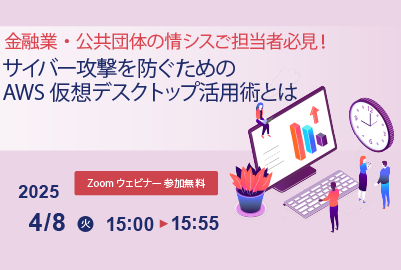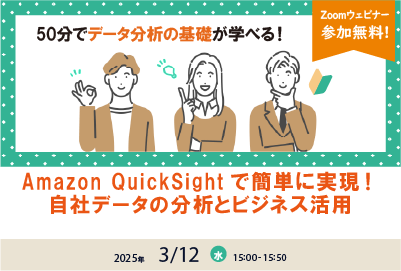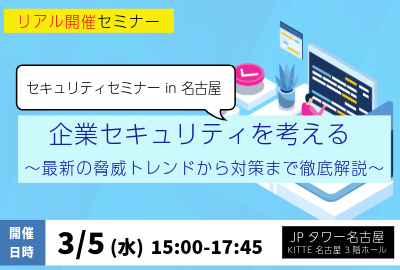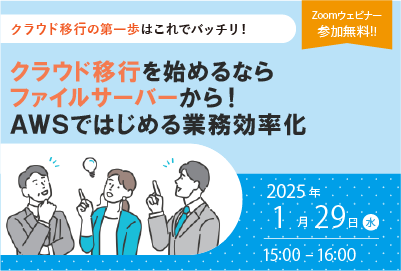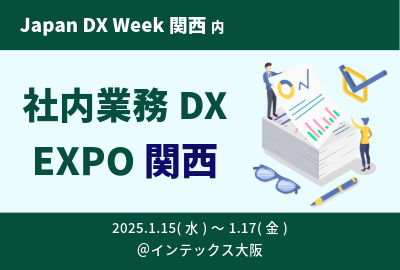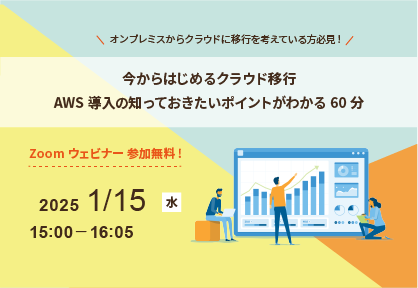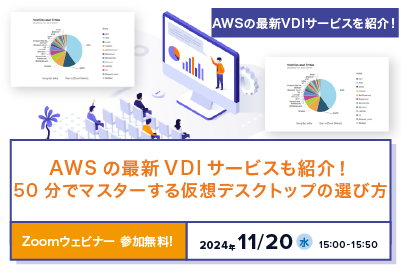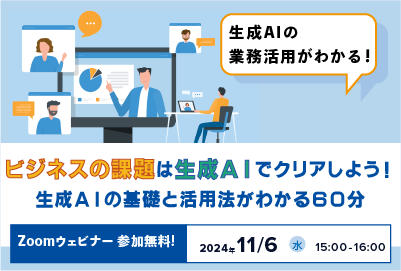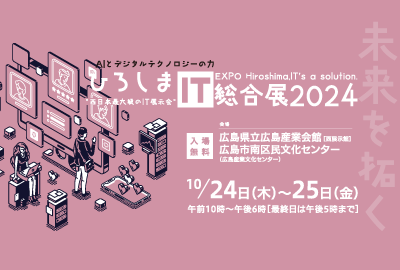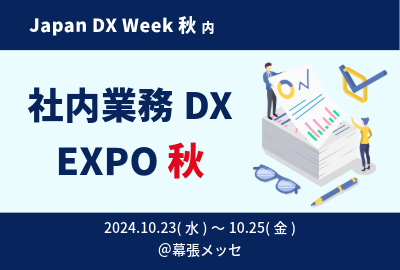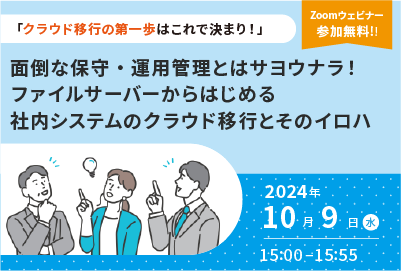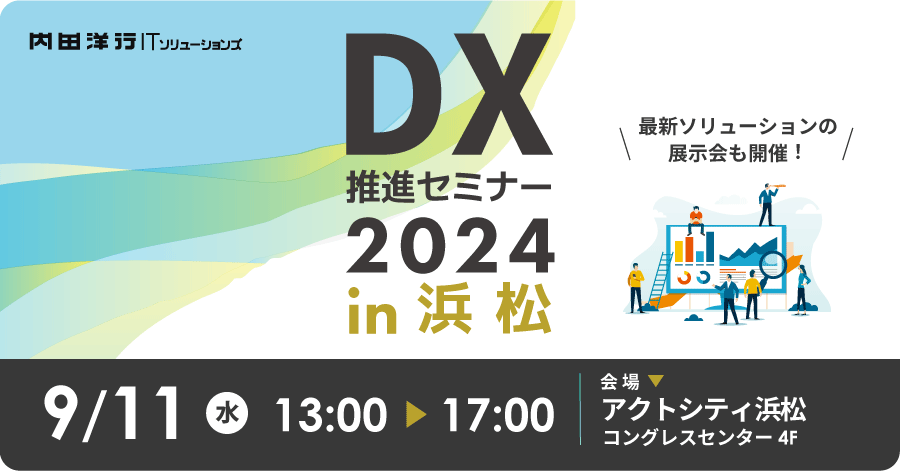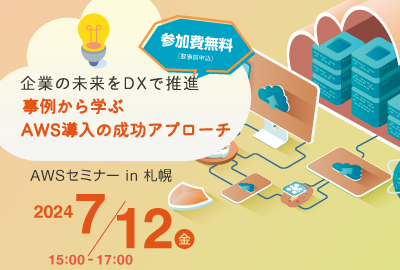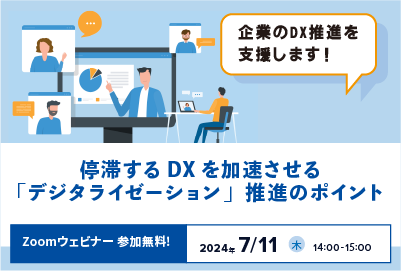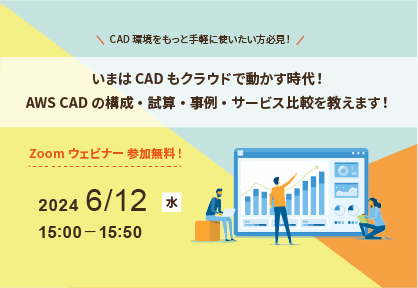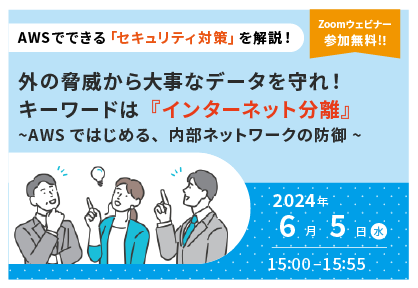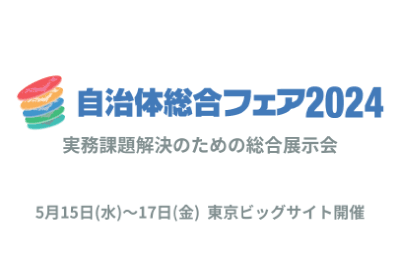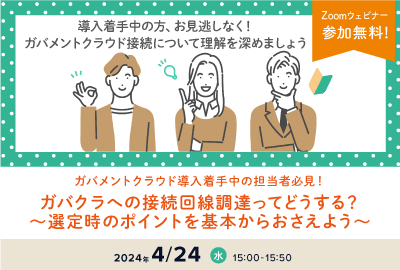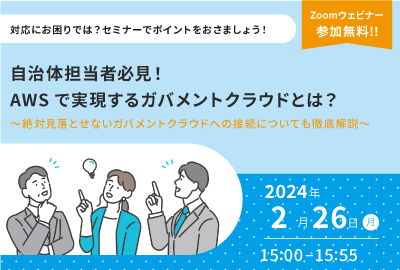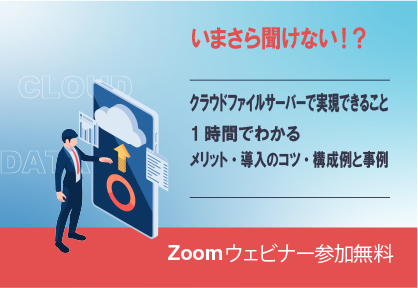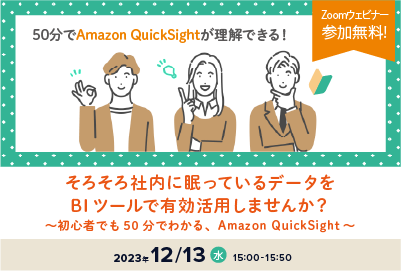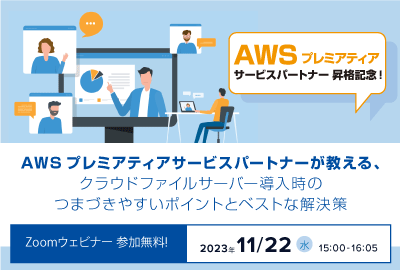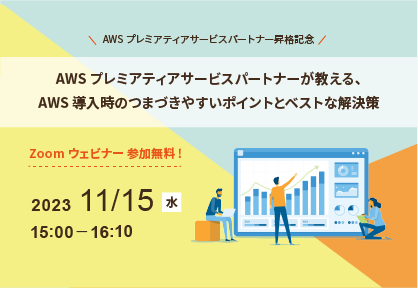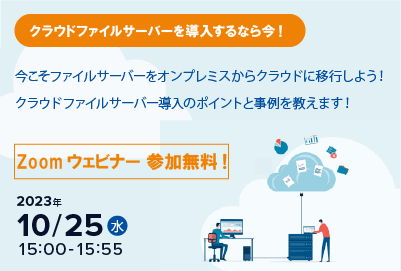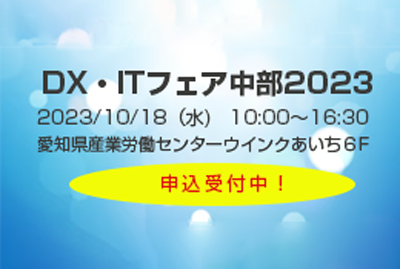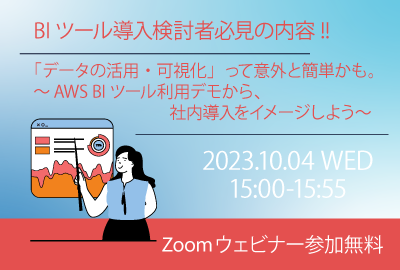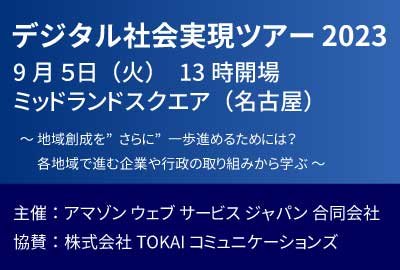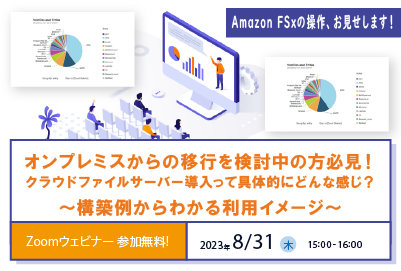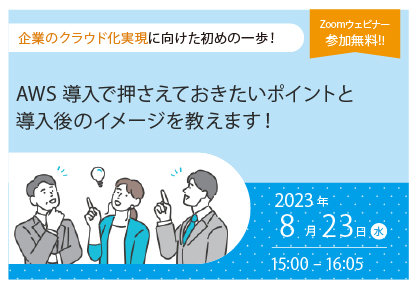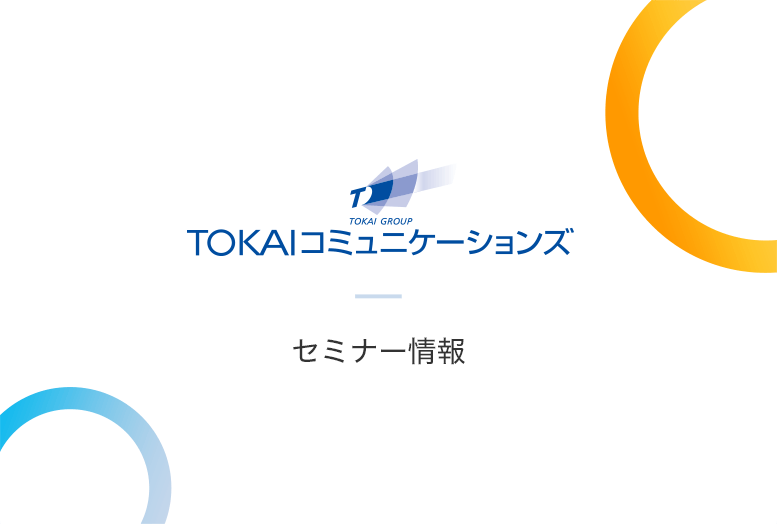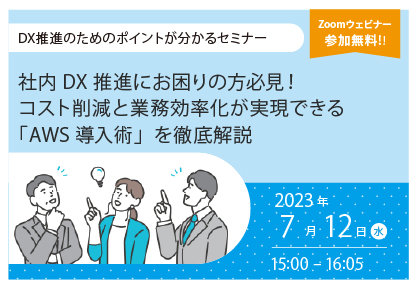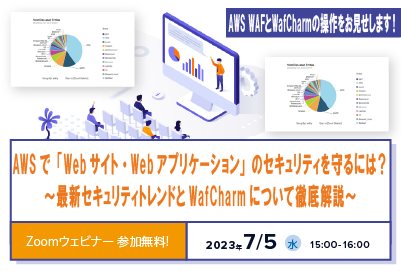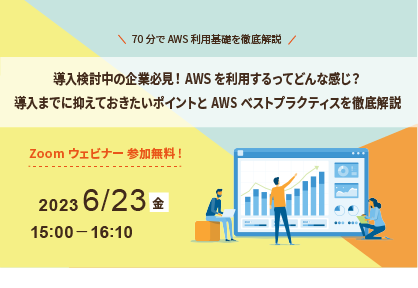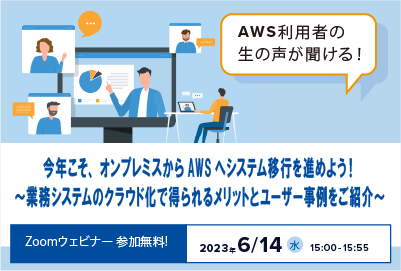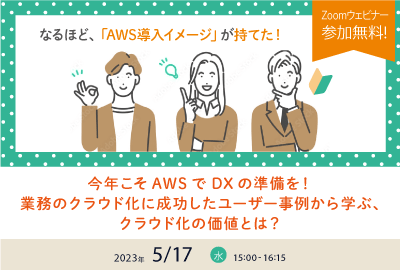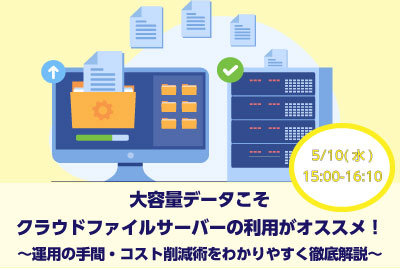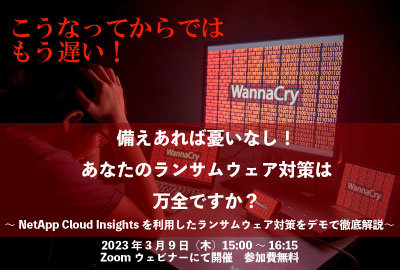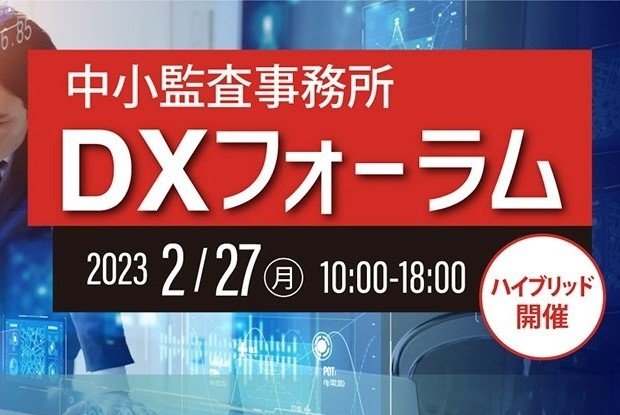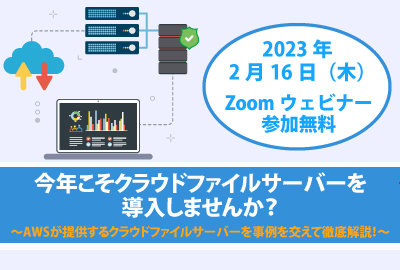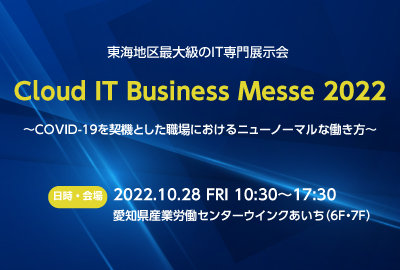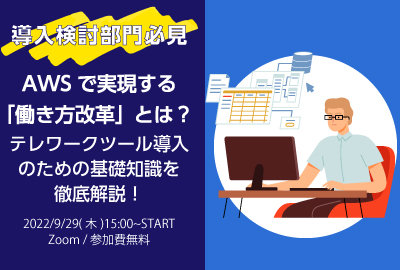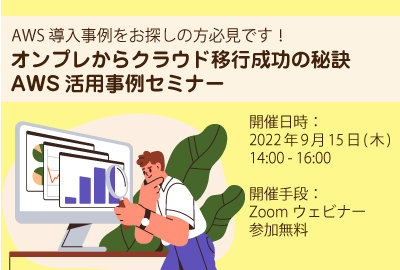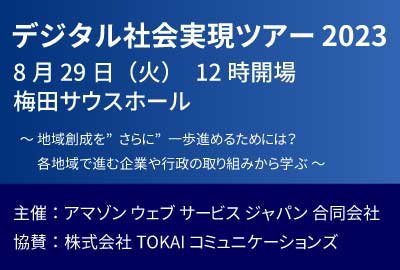「Amazon EC2を使いたいけど、どのインスタンスタイプを選べばいいのか分からない」といった悩みは、AWS初心者が直面しやすいです。
実際、性能不足で業務が遅延したり、過剰スペックで月数十万円のコスト超過に陥った例も珍しくありません。選定に迷ったまま契約すれば、クラウドの恩恵どころか、予算圧迫やパフォーマンス低下を招くリスクがあります。
本記事では、用途・性能・コストの3軸からインスタンスタイプを徹底比較し、最適な選び方を解説します。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
目次
Amazon EC2のインスタンスタイプとは
Amazon EC2を活用する上で最初の壁となるのが「インスタンスタイプの選定」です。ここでは、インスタンスタイプの基本的な定義と、その選択がパフォーマンスやコストにどう影響するのかを解説します。
Amazon EC2 の基本的な仕組み・料金については以下の記事で詳しくご紹介しています。
是非あわせてご参考ください。
Amazon EC2とは?料金・インスタンスタイプ・使い方を初心者向けにわかりやすく解説
インスタンスタイプの定義
Amazon EC2のインスタンスタイプとは、一言でいえば「パソコンの性能カタログ」であり、パソコンを選ぶ際にCPUとメモリを検討するのと同じです。AWSでも、必要に応じたタイプを選ぶだけで、すぐにクラウド上で仮想マシンを立ち上げられます。CPUやメモリ、ストレージ容量、ネットワーク性能といった構成があらかじめテンプレートとして定義されており、ユーザーはその中から必要に応じたタイプを選ぶだけで、すぐにクラウド上で仮想マシンを立ち上げられます。
例えば、画像編集などCPU使用率が低い作業には軽量な構成の「Tファミリー」、高負荷なデータ処理には「Cファミリー」や「Rファミリー」など、用途に応じて最適なタイプが用意されています。
これにより、物理サーバーのように1台ずつ機器を選定・構築する手間を省き、柔軟かつスピーディなシステム構築が可能です。
コストと性能への影響
インスタンスタイプの選定は、Amazon EC2の運用コストと処理能力を大きく左右します。選んだタイプが業務に対して過剰なスペックであれば、使いきれないリソースに対して高額な費用を支払うことになります。
逆に、必要な性能を満たしていないインスタンスを選ぶと、処理が遅れたり、サービスの応答性が低下するなどのパフォーマンスリスクが生じるでしょう。
オンプレミス(自社サーバー)と比較しても、Amazon EC2は契約変更が柔軟で、タイプの変更やスケールの調整が容易に行えるという利点がありますが、最初の選定ミスが業務全体に波及する可能性がある点は変わりません。
したがって、インスタンスタイプの理解と選定は、クラウド運用における「コスト最適化」と「性能確保」を同時に実現するための第一歩といえるのです。
インスタンスタイプに含まれる要素
Amazon EC2のインスタンスタイプを正しく選ぶためには、「ファミリー」「世代」「サイズ」という3つの基本要素を理解することが不可欠です。ここでは、それぞれがインスタンス選定にどのように関係するのかを解説します。
ファミリー
「ファミリー」は、Amazon EC2インスタンスの特性別カテゴリです。CPUやメモリ、ストレージの最適化方向に応じて複数のファミリーが用意されており、用途に応じた選定の第一基準になります。
主なファミリーは以下の通りです。
- Tファミリー/Mファミリー(汎用):開発環境や中小規模の業務アプリケーションに適したバランス型。
- Cファミリー(コンピューティング最適化):バッチ処理やAPIサーバーなど、CPU性能が求められる用途向け。
- Rファミリー(メモリ最適化):データベースやキャッシュサーバーなど、大容量メモリが必要な処理に対応。
- G/Pファミリー(GPU最適化):機械学習、動画処理、レンダリングなどGPU依存型の業務に最適。
- I/Dファミリー(ストレージ最適化):大量I/Oを処理するログ収集や分析処理に活躍。
このように、ファミリーの選定はアプリケーションの特性を理解することから始まります。
世代
Amazon EC2のインスタンスには、それぞれ「世代番号」が付与されています。例えば、「m5」「c6g」「r7g」などがそれに該当し、数字が大きいほど新しい世代を表します。
新世代では、CPU性能の向上、消費電力の削減、ネットワーク帯域の拡張、そしてコスト効率の改善といったメリットが加わることが多く、古い世代よりも同価格帯で高パフォーマンスが期待できるでしょう。
そのため、特別な理由がない限りは最新世代を選ぶのが基本方針となります。古い世代は一見コストが安く見えても、性能対価格比で劣るケースが多いため注意が必要です。
サイズ
同じファミリー・同じ世代でも、インスタンスには複数の「サイズ」が用意されています。これは、vCPU(仮想CPU)やメモリ容量のバリエーションを段階的に分けたもので、t3.smallからm5.24xlargeまで多様なラインアップがあります。
例えば「m5ファミリー」では、m5.large(2vCPU/8GB)からm5.24xlarge(96vCPU/384GB)まで、業務の規模や負荷に応じて柔軟に選択できるのが特長です。
また、インスタンスのサイズは後からスケールアップ/ダウンが可能なため、最初はやや控えめなスペックでスタートし、モニタリングしながら調整していく運用もよいでしょう。
主なインスタンスタイプと特徴
Amazon EC2のインスタンスタイプは、その用途と性能によってさまざまな「ファミリー」に分類されます。ここでは代表的な6種類のファミリーを紹介し、それぞれの特性とおすすめの利用シーンを解説します。
Tファミリー(バースト可能な汎用)
Tファミリーは、コストパフォーマンスに優れたバースト性能付きの汎用インスタンスです。通常は控えめなCPU使用率ですが、必要なときだけ一時的にパフォーマンスを引き上げられるのが特徴です。
例えば、定期的にしかアクセスされない業務用Webポータルや、検証環境・開発環境など、CPU使用率が常に高くないワークロードに向いています。小規模スタートアップや新規プロジェクトで「できるだけコストを抑えてクラウドを試したい」という場合にも重宝されます。
ただし、継続的に高い処理性能が求められる用途には不向きなため、CPUクレジットが枯渇しないか定期的に監視しなければなりません。
Mファミリー(汎用)
Mファミリーは、CPUとメモリのバランスが良いオールラウンド型インスタンスです。幅広いユースケースに対応できることから、Amazon EC2における最も標準的な選択肢とされています。
例えば、中小企業の基幹システムや業務用アプリケーションの運用、CMS(WordPressなど)を使ったWebサイト、小〜中規模のデータベースなど、用途を問わず安定した運用が可能です。
「迷ったらMファミリー」と言われるほど汎用性が高く、特定の性能に偏りがない構成を求める企業には最適です。
Cファミリー(コンピューティング最適化)
Cファミリーは、CPU処理能力を最優先に設計された高性能インスタンスです。マルチスレッド処理や短時間での高負荷処理が求められる業務に向いています。
活用例としては、APIサーバーやバッチ処理、科学技術計算、金融系のモデリング演算などが挙げられます。特に、処理速度がビジネス成果に直結するような分野ではCファミリーが強みを発揮するでしょう。
人材業界やメディア業界などで、短時間に大量のアクセスが集中するサービスを運用している企業におすすめです。
Rファミリー(メモリ最適化)
Rファミリーは、大量のメモリを必要とするアプリケーションに特化したインスタンスタイプです。データの一時保存や検索処理において、メモリ容量がパフォーマンスに直結する場合に威力を発揮します。
主な利用シーンとしては、大規模なリレーショナルデータベース(例:Amazon RDS for PostgreSQL)や、インメモリキャッシュ(例:Redis、Memcached)などが挙げられます。
例えば、ECサイトのレコメンド機能や在庫照会システムなど、高速なデータ参照が求められる企業で導入されるケースが多く見られるのが特徴です。
G・Pファミリー(GPU対応)
GファミリーとPファミリーは、いずれもGPU(Graphics Processing Unit)を搭載したインスタンスタイプです。ただし用途に応じて方向性が異なります。
- Gファミリー:グラフィック処理、動画のリアルタイムレンダリング、VFX制作などに最適。ゲーム制作会社や動画制作スタジオなどが活用。
- Pファミリー:ディープラーニング、機械学習トレーニング、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)向け。AI開発企業や研究機関での利用が主。
高性能な分、コストも高くなりやすいため、利用頻度や時間に応じた運用設計が不可欠です。
I・Dファミリー(ストレージ最適化)
IファミリーおよびDファミリーは、高速なディスクI/O性能を求めるストレージ集約型アプリケーションに対応した構成です。高いIOPS(Input/Output Operations Per Second)やスループット性能を必要とする処理に適しています。
例えば、ログデータのリアルタイム分析、ビッグデータ基盤でのETL処理、大規模トランザクションデータの集計処理などが該当します。
特に、データ分析基盤を内製で構築している企業や、高速ログ処理を行うFinTech系企業にとっては、有力な選択肢となるでしょう。
インスタンスタイプの選び方
Amazon EC2を利用する上で最も重要なのが「どのインスタンスタイプを選ぶか」という判断です。ここでは、インスタンスタイプを適切に選ぶための3つの視点を紹介します。
アプリケーション要件の確認
まず最初に行うべきは、「アプリケーションが何を必要としているか」の正確な把握です。具体的には、CPU処理の頻度や強度、メモリ使用量、ストレージ容量やI/O性能といった要件を事前に洗い出すことが欠かせません。
例えば、画像を大量に処理するWebサービスであれば、GPUインスタンス(GファミリーやPファミリー)が適しており、トランザクションの多いデータベースにはメモリ最適化型(Rファミリー)が求められます。
この段階で見誤ると、後から性能不足が発覚し、構成の見直しや移行コストが発生するため、設計初期段階でのリソース要件の精査は不可欠です。
リソース使用状況の把握
要件の仮説だけで選定するのではなく、実際のリソース使用状況を定量的に観測することも重要です。Amazon CloudWatchなどのモニタリングツールを活用すれば、CPU使用率、メモリ使用量、ディスクI/Oの状況を可視化できます。
例えば、t3.mediumインスタンスでCPU使用率が常に80%を超えているようなケースでは、スペック不足が明らかです。その場合は、上位インスタンスへのスケールアップや、別ファミリーへの移行を検討する必要があります。
このように、実運用に基づいたデータ分析により、必要十分なインスタンスを見極めることが、コスト効率とパフォーマンスの両立につながります。
AWS公式ツールの活用
選定に迷った場合や、より客観的な判断をしたいときは、AWSが提供する支援ツールの活用が効果的です。
代表的なツールには以下があります。
- AWS Compute Optimizer
:過去の使用履歴から、最適なインスタンスタイプを自動で提案
- Instance Type Finder
:要件を入力することで、候補インスタンスを一覧表示
これらのツールを活用すれば、自社のワークロードに対して最適なスペックとコストのバランスを保つインスタンスを選出できます。また、複数の候補を比較検討する際にも有用です。
インスタンスタイプ選定時の注意点
Amazon EC2のインスタンスタイプは選択肢が多い分、選定ミスによるコスト超過や性能不足のリスクも潜んでいます。ここでは、インスタンス選定時にありがちな3つの落とし穴と、それを回避するための視点を解説します。
CPUクレジットの制限
Amazon EC2のTファミリー(例:t3.micro、t4g.small)は、バースト可能な汎用インスタンスタイプであり、通常は低いCPU使用率で運用される設計です。高いCPU性能を一時的に利用できる「バースト性能」を持つ一方で、継続的な高負荷処理には向いていません。
ここで登場するのが「CPUクレジット」という仕組みです。これは、CPUを使わない時間に蓄積された分だけ、一時的に高い処理能力を利用できるというAmazon EC2独自の制度です。しかし、クレジットを使い切ってしまうと、CPU性能が制限され、レスポンスが極端に悪化する可能性があります。
したがって、Tファミリーを選ぶ場合は、常時負荷が高くないアプリケーションかどうかを事前に確認することが不可欠です。
オーバースペックによるコスト増
「余裕をもってスペック高めのインスタンスを選んでおこう」と考える企業も少なくありません。しかし、必要以上の性能を持て余し、毎月のランニングコストを無駄に押し上げてしまう典型的な失敗例です。
例えば、実際には1vCPU・2GBメモリで十分な業務に対して、8vCPU・16GBメモリのインスタンスを選定してしまえば、利用率は低くとも費用だけはかかります。これはオンプレミス時代にはなかった、クラウド特有の「見えないコスト肥大化」を招く原因です。
Amazon CloudWatchやAWS Compute Optimizerなどの監視・分析ツールを活用し、「本当にそのスペックが必要か?」を定期的に見直す習慣がコスト最適化につながります。
古い世代の使用による非効率
Amazon EC2では、同じインスタンスタイプでも「m4」「m5」「m6g」など、世代によって性能と料金が異なります。古い世代を継続利用しているケースでは、最新世代の方が安価で高性能という逆転現象も少なくありません。
例えば、第5世代(m5)より第7世代(m7g)の方が、ArmベースのGravitonプロセッサを搭載しており、コストパフォーマンスが大幅に向上しています。
特別な理由がない限りは、常に最新世代の活用を基本とし、定期的なアップデートを検討することが、クラウド運用における効率性の鍵となります。
コスト最適化の方法
Amazon EC2は柔軟なインフラである一方、運用次第ではコストが肥大化するリスクもあります。ここでは、コスト最適化を実現するための基本的な手法として、契約方式の使い分け、割引プランの活用、そして性能と費用のバランスを取る考え方を解説します。
オンデマンド・リザーブド・スポットの使い分け
まず基本となるのが、インスタンスの「購入モデル」の選び方です。Amazon EC2には、以下の3つの契約方式が用意されています。
- オンデマンドインスタンス:使用した分だけ従量課金。短期間の利用や予測不能なワークロードに適しています。
- リザーブドインスタンス:1年または3年の利用を前提にすることで割引が受けられます。長期的に安定した稼働が見込まれる業務システムに最適です。
- スポットインスタンス:空きキャパシティを活用することで、最大90%のコスト削減が可能。ただし、AWSの都合で中断される可能性があるため、バッチ処理や一時的な分析業務に向いています。
これらを業務の特性に応じて組み合わせることで、無駄のない構成を実現できます。
Savings Plansの活用
Amazon EC2の利用量がある程度予測できる場合は、Savings Plansの導入が有効です。これは、「1年もしくは3年間、一定量の利用をコミットする」ことで、柔軟なインスタンス運用を保ちながらも割引を受けられる制度です。
大きな特徴は、従来のリザーブドインスタンスと異なり、インスタンスタイプやリージョンに縛られず、自由な運用が可能である点となります。特にCompute Savings PlansはAmazon EC2の利用全体に適用されるため、業務内容や構成が変化しやすい企業でも安心して導入できます。
コストと性能のバランス
最後に重要なのは、単純な安さだけを追わないことです。必要な処理性能を満たさないインスタンスタイプを選べば、パフォーマンス不足によって作業効率が低下し、かえってコストが増す可能性があります。
例えば、スポットインスタンスはコスト面では魅力的ですが、処理の途中で中断されると再処理が必要になり、全体として非効率になるケースもあります。
したがって、「この構成は最小コストで最大の成果を出せているか?」という視点で、コストと性能のバランスを見極める判断力が不可欠です。
まとめ
Amazon EC2のインスタンスタイプ選定は、性能・用途・コストの3軸で最適な構成を見極めることが重要です。適切なタイプを選ぶことで、クラウドのパフォーマンスを最大化しつつ、無駄なコストを抑えられます。
ただし、要件の把握やコスト試算には専門的な知見が必要になる場面も少なくありません。そうした場合は、AWS導入支援に実績のあるTOKAIコミュニケーションズのような信頼できるパートナー企業を活用することで、より確実な構築と運用が実現できます。お気軽にご相談 ください。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
関連サービス
おすすめ記事
-
2024.08.28
セキュリティ・バイ・デザイン入門|AWSで実現するセキュリティ・バイ・デザイン
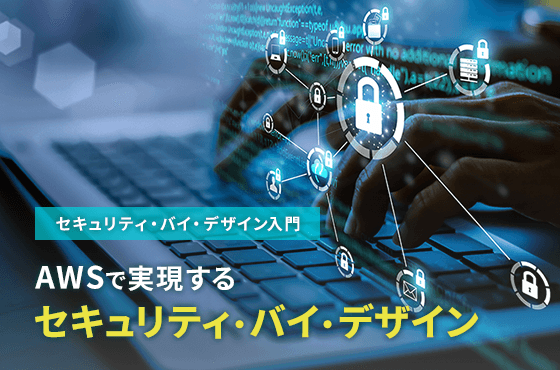
-
2024.04.10
AWSを使って障害に強い環境を構築するポイント(システム監視編)
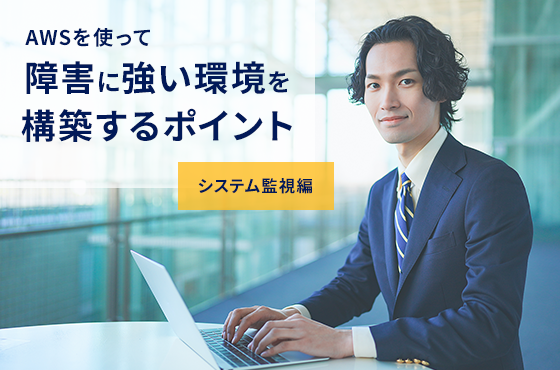
-
2023.07.04
クラウド利用時に知っておくべきセキュリティ知識【基礎編】

-
2023.06.15
AWSでゼロトラストセキュリティを実現する方法や、メリットをわかりやすく解説!

-
2023.06.05
AWSのセキュリティ対策は大丈夫? オンプレミスとの違いやセキュリティ関連のAWSサービスを紹介!