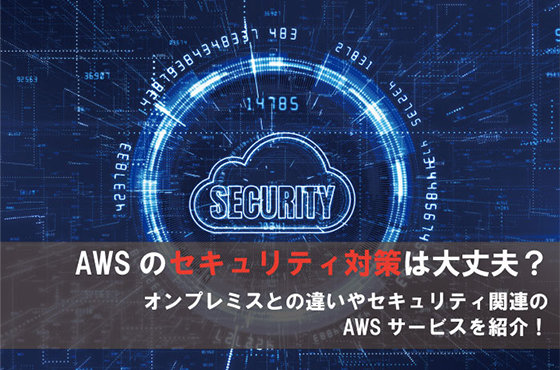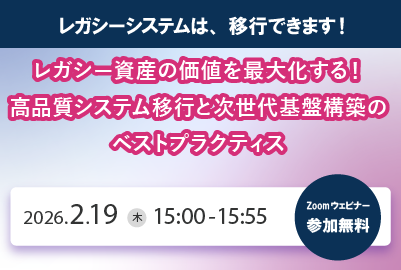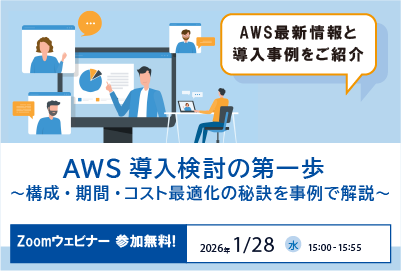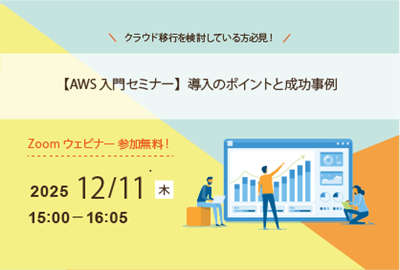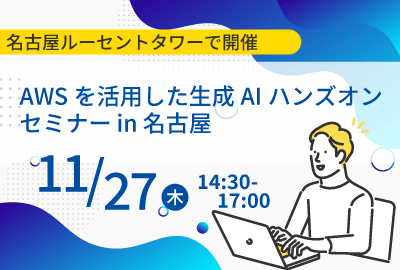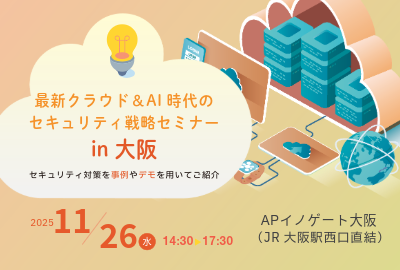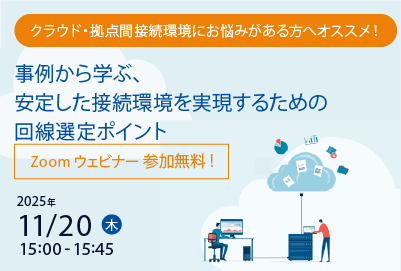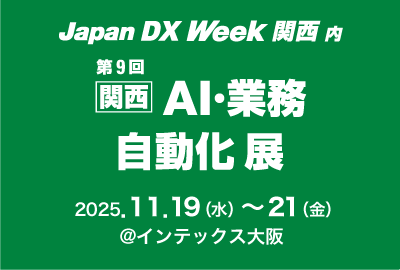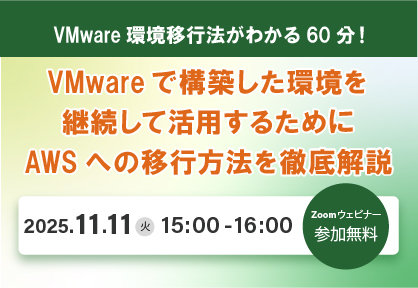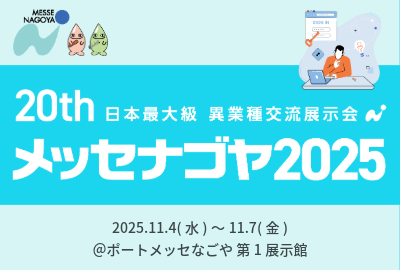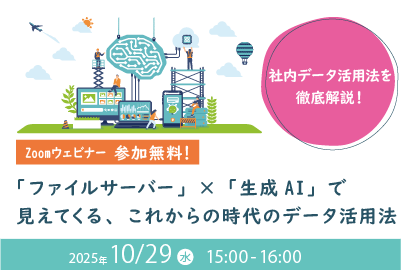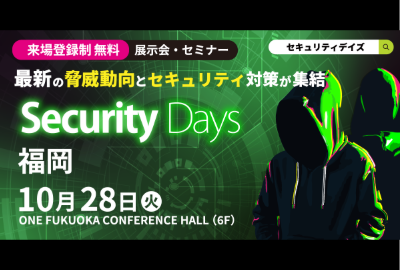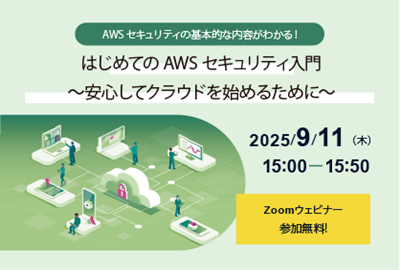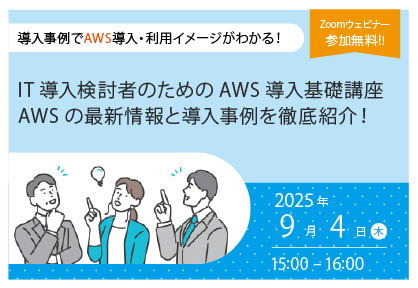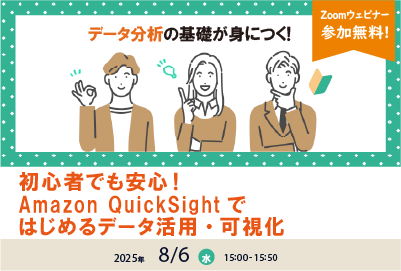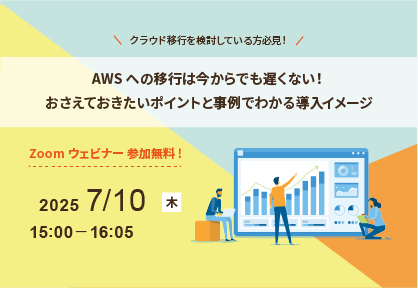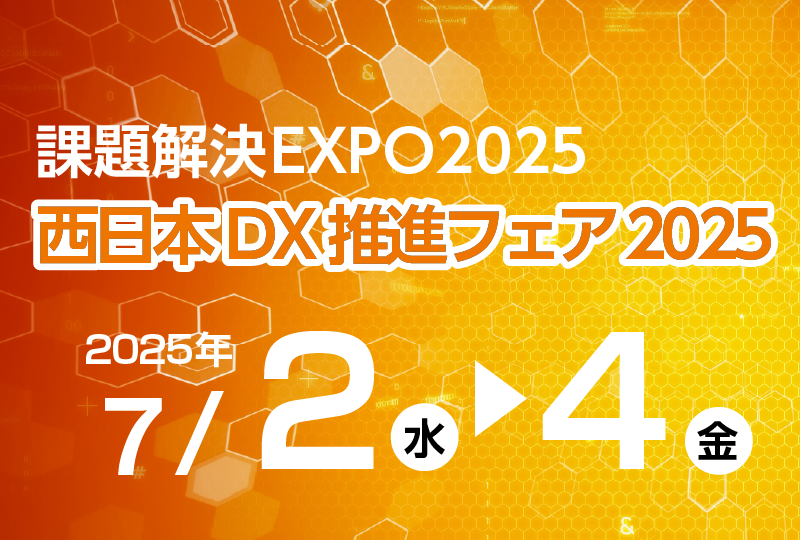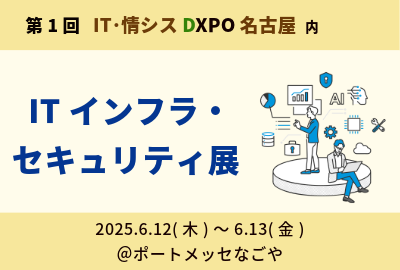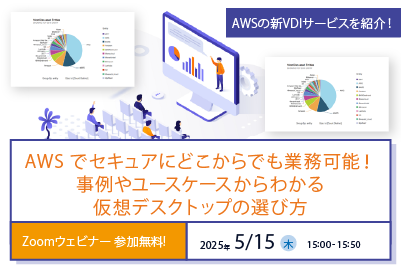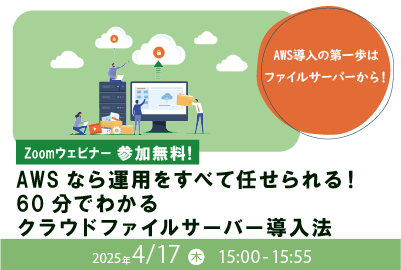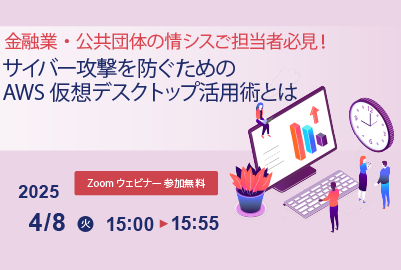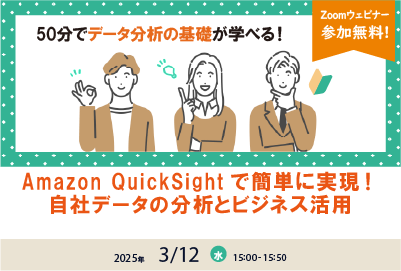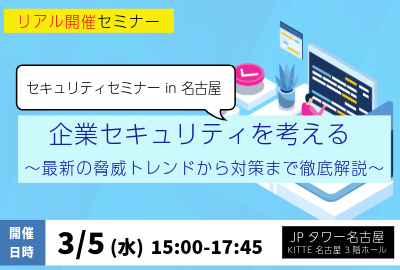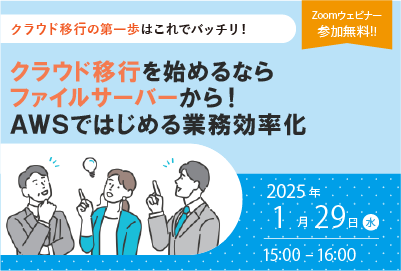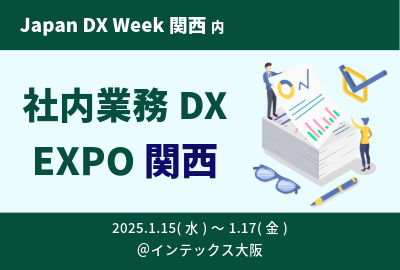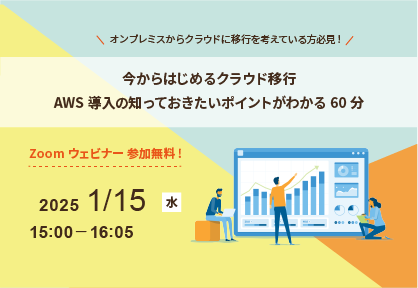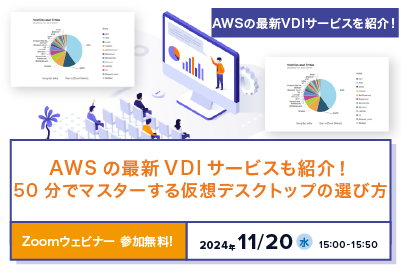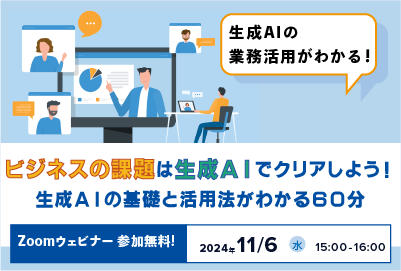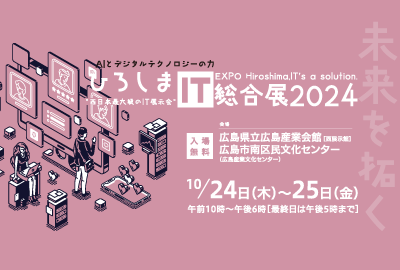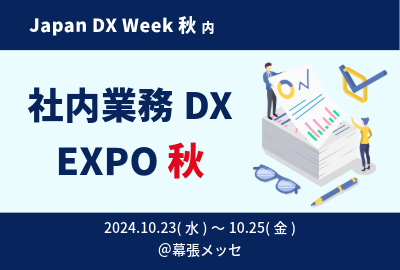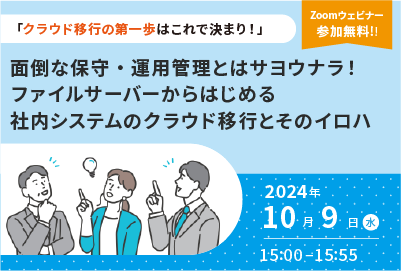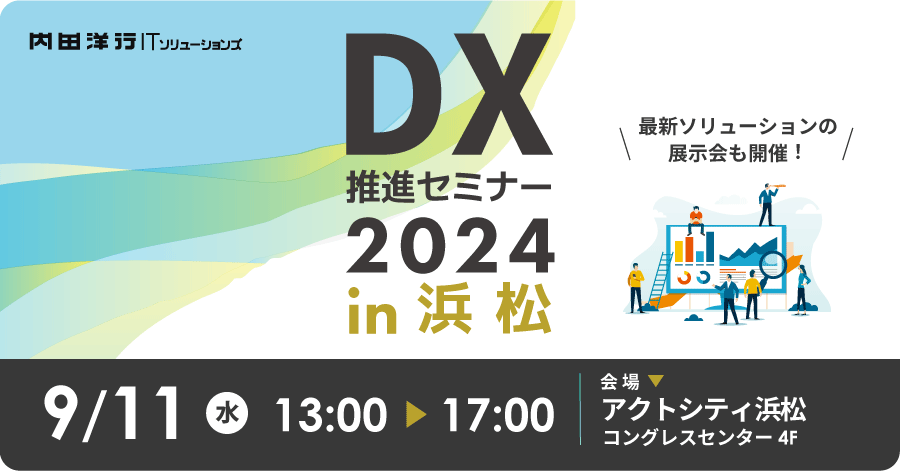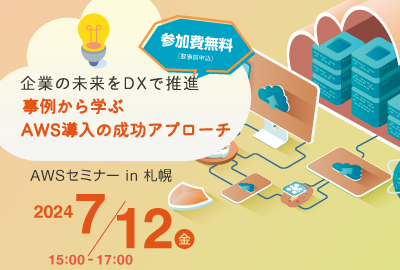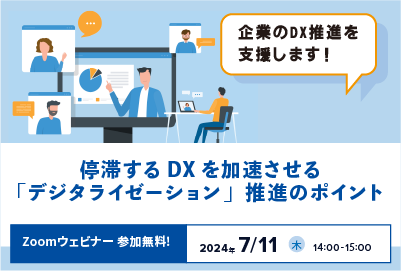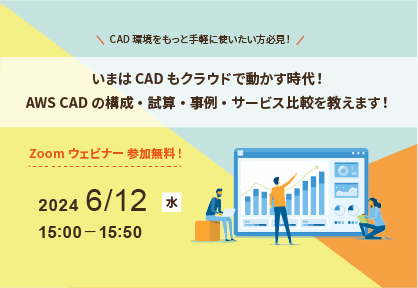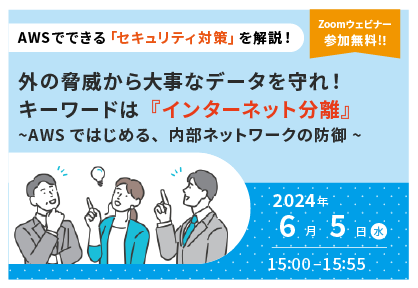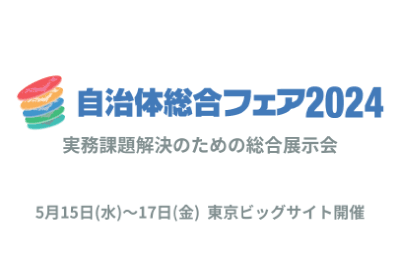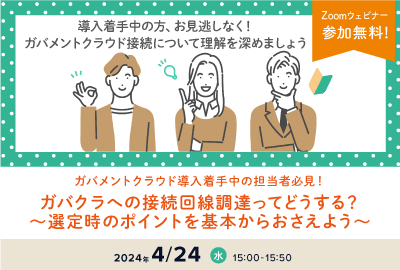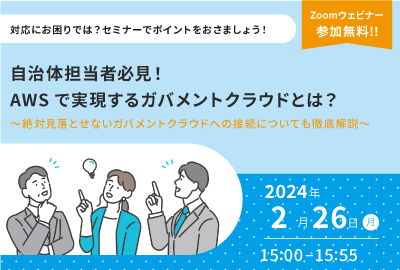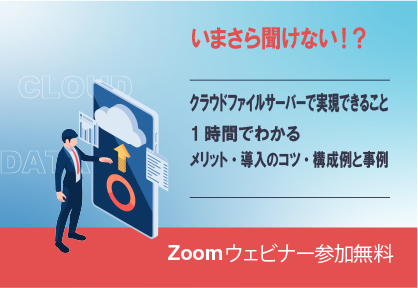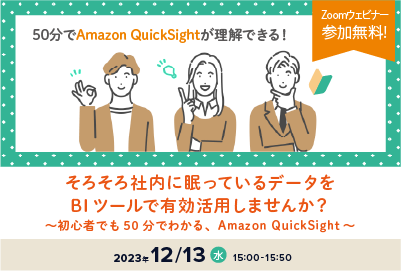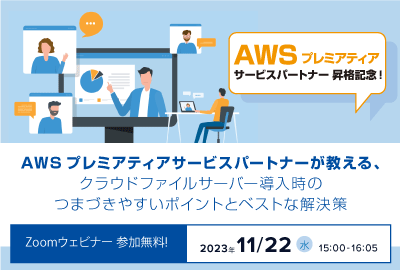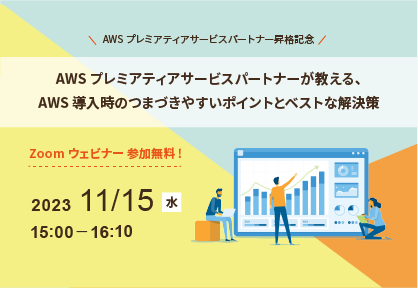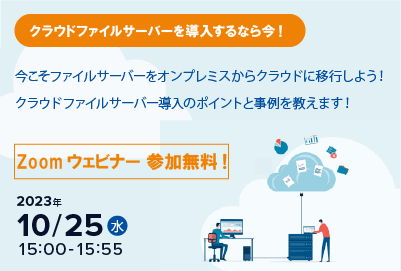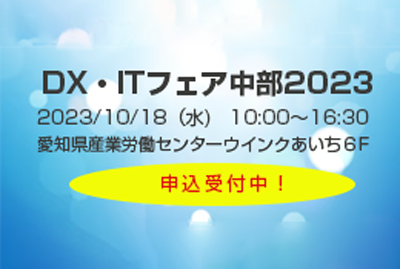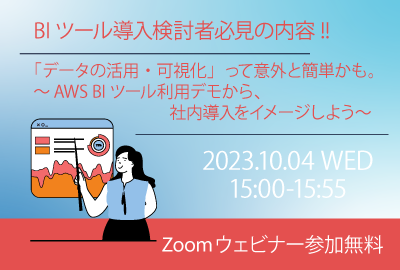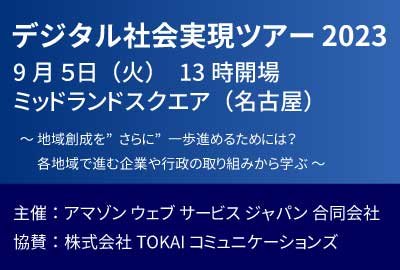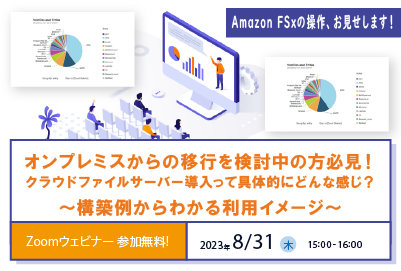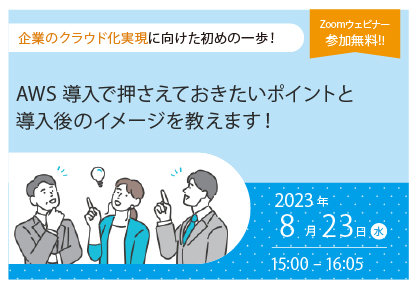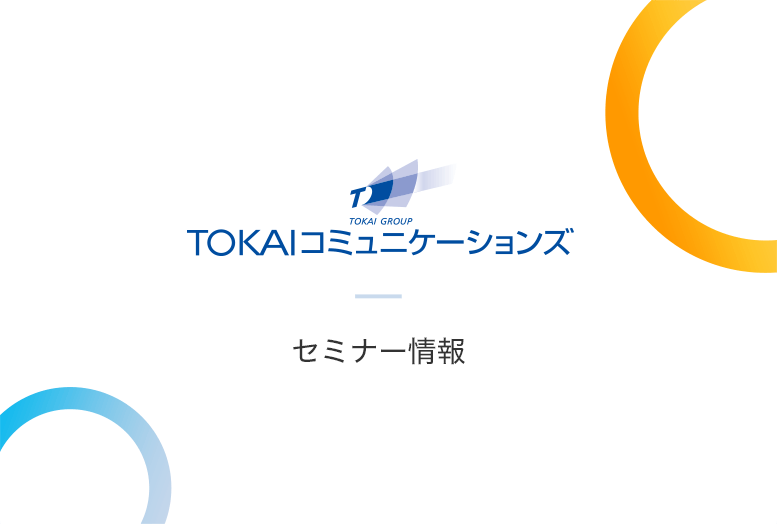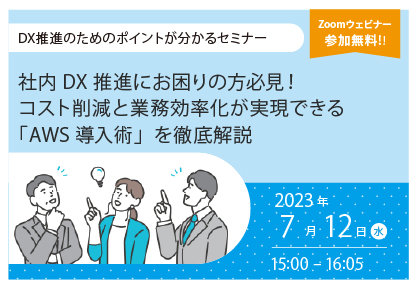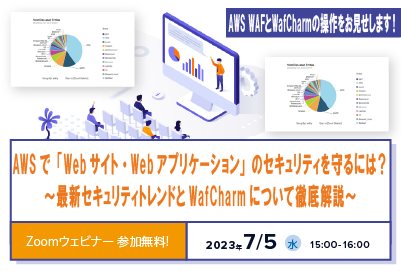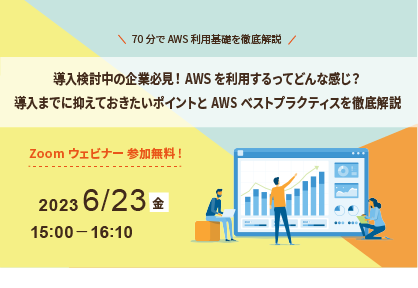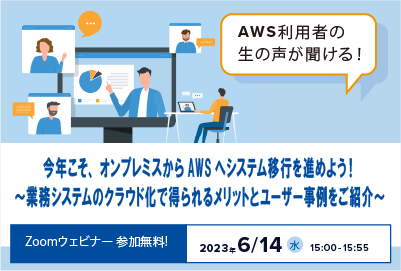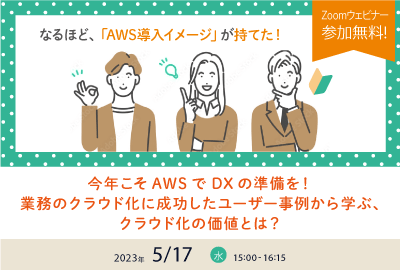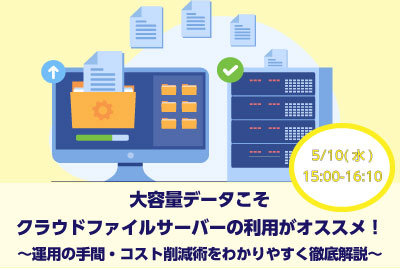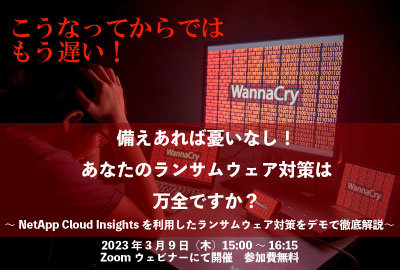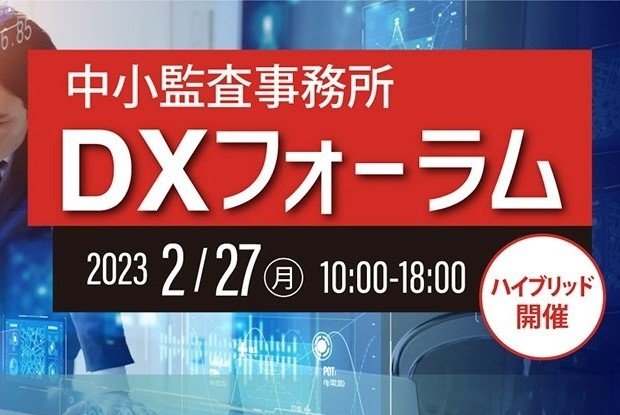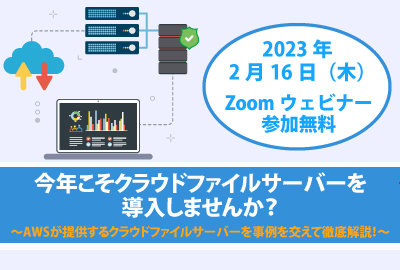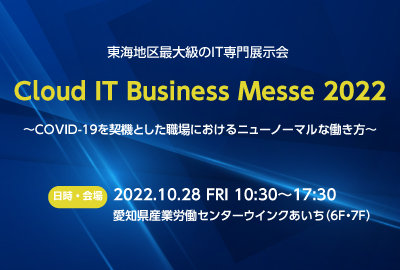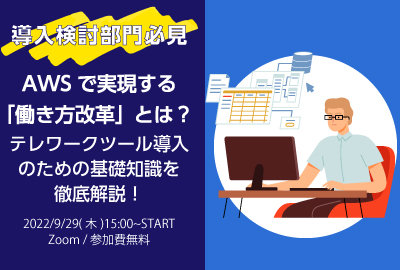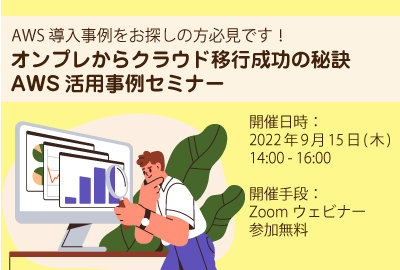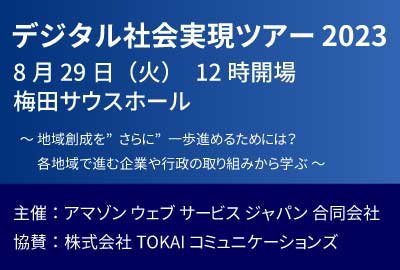クラウドストレージを検討する上で、AWSの「Amazon S3」は外せない選択肢の一つです。容量無制限で高い耐久性・可用性を備え、世界中の企業が信頼を寄せるストレージとなっています。
本記事では、Amazon S3の基本的な仕組みやメリット、料金体系、活用方法について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
Amazon S3とは
Amazon Simple Storage Service(以下、S3)は、Amazon Web Services(AWS)が提供するオブジェクトストレージサービスです。
データ容量の制限がなく、高い耐久性(99.999999999%)と可用性(99.99%以上)を誇ることから、世界中の企業でデータの保存・配信・アーカイブ用途に広く採用されています。
なぜS3が多くのユーザーに選ばれているのかというと、運用負荷が少なく、拡張性と信頼性に優れているためです。クラウド上で動的にスケールでき、インフラ管理なしに大量のデータを扱えるのは大きな強みといえます。
さらに、料金は従量課金制のため、必要な分だけ支払えばよく、コスト管理もしやすい点も魅力の一つです。
S3を利用する際に押さえておきたい基本的な概念がいくつかあります。まずバケットとは、S3上に作成されるデータの「コンテナ」のようなもので、すべてのデータ(オブジェクト)はこのバケット内に保存されます。バケット名はグローバルで一意でなければなりません。
次にオブジェクトは、実際に保存されるファイルそのものを指します。最大サイズは5TBで、オブジェクトごとにメタデータやアクセス制御情報も付与可能です。
キーとは、各オブジェクトに割り当てられる名前で、バケット内でオブジェクトを一意に識別するために使用されます。フォルダ構造のように見せることも可能ですが、あくまでキーの命名規則により階層的に扱っているだけです。
また、S3ではリージョンの選択も重要です。データが物理的に保存される地理的な場所を意味し、日本国内なら「アジアパシフィック(東京)」リージョンが一般的となります。データの遅延、法的要件、耐障害性を考慮しながら、適切なリージョンを選ぶことが推奨されます。
このように、S3はシンプルでありながら堅牢な設計となっており、クラウド時代のストレージとして非常に高い汎用性を持っているのが特徴です。
Amazon S3の5つの主なメリット
S3には、主に以下のメリットがあります。
- 高い耐久性と可用性(イレブンナイン)
- セキュリティとアクセス管理
- コストパフォーマンスに優れた従量課金制
- 無制限のスケーラビリティと柔軟な構成
- 静的コンテンツのホスティングにも対応
それぞれ解説します。
高い耐久性と可用性(イレブンナイン)
S3は、オブジェクトごとに「99.999999999%」という極めて高い耐久性を実現しており、保存されたデータが失われる可能性はほぼゼロに近いといえます。
これは、S3がデータを自動的に複数のアベイラビリティゾーン(AZ)に分散して保存し、定期的に整合性を検証しながら破損したデータを修復しているためです。
また、SLA(サービスレベルアグリーメント)でも「99.99%以上」の高可用性が保証されており、長期間安定してサービスを利用し続けられる信頼性の高さは、業務用の基盤として安心して導入できる理由の一つです。
セキュリティとアクセス管理
S3は、クラウド上で重要なデータを安全に管理するためのセキュリティ機能が豊富に備わっています。
データは保存時・転送時ともに暗号化されており、AWS管理のキー(SSE-S3)のほか、カスタマー管理キー(SSE-KMS)も選択可能です。アクセス制御にはIAMポリシーやバケットポリシー、ACLがあり、柔軟に細かく権限設定できます。
また、公開設定ミスを防ぐ「Block Public Access」や、操作履歴を記録できる「AWS CloudTrail」「サーバーアクセスログ」など、企業のコンプライアンス遵守や内部統制にも対応できる設計となっており、安心してデータ運用が可能です。
コストパフォーマンスに優れた従量課金制
S3は「使った分だけ支払う」従量課金制を採用しており、初期費用や月額固定費が不要です。保存容量(GB単位)、リクエスト数、データ転送量などが主な料金構成要素であり、利用量に応じて柔軟にコストが変動します。
オンプレミスと比較すると、ハードウェアの購入や保守、人件費といった間接的コストがかからず、スモールスタートにも最適です。また、ストレージクラスを適切に選択することで、アクセス頻度に応じた最適なコスト設計が可能です。
料金シミュレーターやコスト分析ツールも用意されており、企業でも予算管理しやすい環境が整っています。
無制限のスケーラビリティと柔軟な構成
S3は、保存可能なデータ容量やオブジェクト数に事実上の上限がなく、利用者がスケールの制限を意識する必要がありません。
例えば、Webサービスのログデータを1日数TB単位で保存するケースでも、事前の容量設計や再構成は不要です。大規模データのアップロードには「マルチパートアップロード」機能が利用でき、ネットワークトラブルにも強い分割送信が可能です。
また、ライフサイクルルールやバージョニングといった構成機能により、柔軟なデータ管理やコスト最適化が実現できます。スタートアップから大企業まで、規模を問わず活用できる柔軟性はS3の大きな魅力です。
静的コンテンツのホスティングにも対応
S3は、HTMLやCSS、画像などの静的ファイルをWebで公開できる「静的ウェブサイトホスティング」機能を備えています。
これにより、Webサーバーを別途用意せずとも、簡単な社内ポータルやキャンペーン用LP(ランディングページ)をサーバーレスで運用できます。公開設定やリダイレクトルールもGUI上で簡単に設定でき、HTTPS対応もCloudFrontとの連携で可能です。
WordPressのような動的処理はできませんが、読み込み速度や運用の手軽さ、そして低コストという点で、小規模〜中規模のWebサイトには適した選択肢となります。
Amazon S3のストレージクラス
S3には、以下のストレージクラスが存在します。
- S3 Standard
- S3 Intelligent-Tiering
- S3 Standard-IA(低頻度アクセス)
- S3 One Zone-IA
- S3 Express One Zone
- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive
ここでは、ストレージクラスについて一部を抜粋してご説明します。
S3 Standard
S3 Standardは、最も一般的で汎用的なストレージクラスです。高頻度でアクセスされるデータに最適化されており、99.99%の可用性と11ナイン(99.999999999%)の耐久性を誇ります。
低レイテンシと高スループットに対応し、Webアプリケーション、動的なWebサイト、モバイルアプリ、データ分析基盤など、あらゆるユースケースに適しています。複数のアベイラビリティゾーンに自動的にデータを複製するため、災害時にもデータ損失のリスクがきわめて低く、ビジネスにとって安心できる選択肢です。
S3 Standard-IA(低頻度アクセス)
S3 Standard-IAは、アクセス頻度が低いものの、必要なときには即時にデータを取得したいといったニーズに応えるストレージです。
Standardと同等の耐久性と可用性を持ちつつ、ストレージコストが低く設定されているのが特徴です。ただし、30日間の最低保存期間があり、データ取得にはリクエスト料金がかかります。
バックアップデータやアーカイブ済みのログ、法律対応で保管が必要な記録など、即時アクセスが必要な長期保管データに最適なクラスです。
S3 One Zone-IA
S3 One Zone-IAは、他のクラスとは異なり、単一のアベイラビリティゾーンにのみデータを保存するため、コストをより抑えられるのが最大のメリットです。
耐久性は高く保たれているものの、複数AZに分散されないため、可用性や障害耐性はやや劣ります。その分、Standard-IAよりも約20%安く、コスト重視の用途に適しています。
再取得可能なコンテンツやテストデータ、動画のトランスコード後ファイルなど、失っても業務に致命的でないデータ向けにおすすめです。
S3 Intelligent-Tiering
S3 Intelligent-Tieringは、アクセス頻度に応じて自動でデータを最適なストレージ階層へ移行する仕組みを持ったクラスです。
高頻度アクセス層・低頻度アクセス層・アーカイブ層の間で自動管理され、ユーザーが手動でクラス変更を行う必要がありません。アクセスパターンの予測が難しいデータや、利用頻度が時間と共に変化するデータに最適です。
低頻度・アーカイブ層への移行では通知や追加料金が発生しないため、コストを意識しながらも運用の手間を減らしたい企業にとって理想的な選択肢です。
S3 Glacier
S3 Glacierは、アーカイブ用途に特化した超低コストなストレージクラスファミリーです。
データ復元に時間がかかる特性があるため、即時の読み出しは不要なものの、長期的な保存が必須なケースに適しています。 例えば、監査ログや研究データ、法的に保存が義務付けられた文書などが該当します。
このファミリーには「S3 Glacier Instant Retrieval」「S3 Glacier Flexible Retrieval」「S3 Glacier Deep Archive」の3つのクラスがあり、復元時間とコストが異なります。 例えば、「S3 Glacier Flexible Retrieval」は数分~数時間で復元可能ですが、「S3 Glacier Deep Archive」は復元に12時間程度要するものの、月額$0.00099 USD/GBからと、圧倒的に安価な料金でデータを保持できます。
Amazon S3の主なユースケースとは?
S3の主なユースケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- バックアップ&災害対策(BCP)用途としての活用
- 長期アーカイブとしてのコスト削減
- 静的Webサイト・コンテンツのホスティング
それぞれのユースケースの詳細と、具体的な金額についても解説します。
バックアップ&災害対策(BCP)用途としての活用
S3とAWS Storage Gatewayを組み合わせることで、オンプレミスのデータをクラウドに自動バックアップできます。
例えば、ファイルゲートウェイやボリュームゲートウェイを経由すれば、既存のアプリやバックアップソフトからそのままS3へ保存可能です。テープライブラリを仮想化するテープゲートウェイもあり、GlacierやDeep Archiveへの長期保存も容易です。
複数のAZやリージョンに分散されたデータは、災害時も迅速に復旧でき、BCP(事業継続計画)において非常に高い信頼性を発揮します。
長期アーカイブとしてのコスト削減
法律や規制で長期保存が求められる監査ログや研究データなどは、GlacierおよびGlacier Deep Archiveの活用が効果的です。
月額0.00099 USD/GBからと超低コストで、法律対応や大量アーカイブ用途に最適です。Standard‑IAへの自動移行をLifecycleルールで組むと、使用頻度に応じてコスト最適化が可能です。
さらに、S3のバージョニングやObject Lockを使えば、削除防止などのコンプライアンス対応も担保でき、安心して長期保存が行えます。
静的Webサイト・コンテンツのホスティング
S3の静的ウェブホスティング機能を使えば、HTML・CSS・画像などの公開を、Amazon EC2などのサーバーを使わずに実現できます。
転送は Amazon CloudFront と組み合わせることでHTTPS対応が可能になり、配信速度やセキュリティを向上させつつサーバーレスな運用が可能です。キャンペーンページや社内ポータルなどに適しており、運用コストや運用負荷を大幅に削減できます。
読み込み速度の改善や設定の簡便さもあり、中小規模サイトに有効です。
料金計算の具体例
画像を中心とした中小規模のWebサイトをS3で運用するケースを想定してみましょう。1枚あたり1MBの画像を10万点保存し、合計保存容量が100GBに達すると仮定します。
保存先は「S3 Standard」を利用するとして、東京リージョンでの月額料金は以下のようになります。
- 画像ファイル100GBの保存:月額 約250円
- 月間100万PV(転送量約80GB想定)のデータ転送料:約800円
- GETリクエスト100万回のリクエスト料金:約50円
これらを合算すると、月額の総コストは約1,100円程度です。
- ※ 実際の料金は、為替レートや料金改定により変動する可能性があります。
サーバーやHDDの購入・保守、人件費、バックアップ管理といったオンプレミス運用にかかる初期費用・固定費と比べて圧倒的に安価です。
さらに、スケーラビリティや耐障害性の面でもクラウドならではの柔軟性があり、突発的なアクセス増にも強く、運用負担も軽減されます。少額から始められるクラウドの利点を体感できる、非常に現実的な導入モデルといえるでしょう。
まとめ
Amazon S3は、圧倒的な耐久性と柔軟な料金体系、高度なセキュリティを兼ね備えたクラウドストレージです。
バックアップやアーカイブ、Webホスティングなど、企業規模を問わずさまざまな用途に活用できます。初めてAWS導入を検討される方でも、構成の自由度とコスト最適化のバランスが取れたS3は有効な選択肢です。
TOKAIコミュニケーションズでは、AWS導入から運用までを一貫してサポートしています。ネットワーク設計や閉域網接続、リセール、運用管理サービスなど、多角的な支援でお客様の課題を解決します。
まずは「今から始めるAWS完全ガイド 」をダウンロードし、AWSへの理解を深めていきましょう。お困りの際はお気軽にご相談
ください。
人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド
関連サービス
おすすめ記事
-
2024.08.28
セキュリティ・バイ・デザイン入門|AWSで実現するセキュリティ・バイ・デザイン
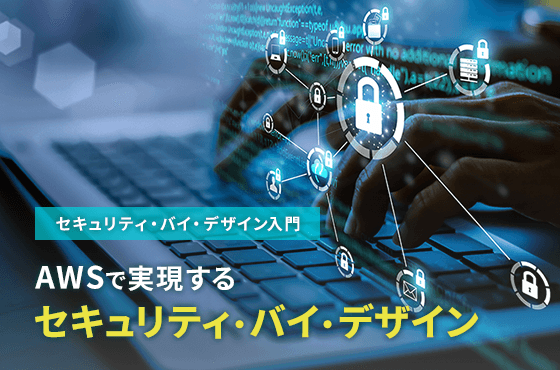
-
2024.04.10
AWSを使って障害に強い環境を構築するポイント(システム監視編)
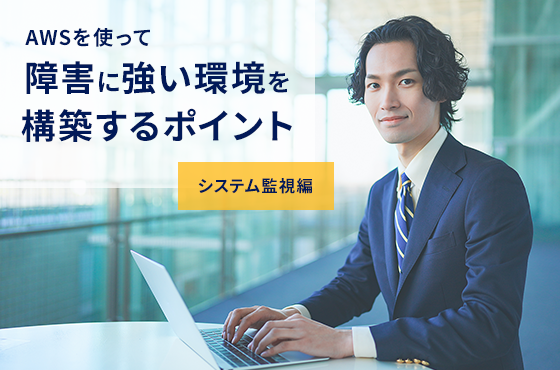
-
2023.07.04
クラウド利用時に知っておくべきセキュリティ知識【基礎編】

-
2023.06.15
AWSでゼロトラストセキュリティを実現する方法や、メリットをわかりやすく解説!

-
2023.06.05
AWSのセキュリティ対策は大丈夫? オンプレミスとの違いやセキュリティ関連のAWSサービスを紹介!