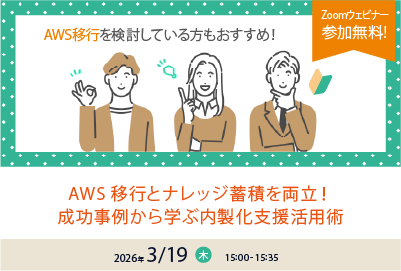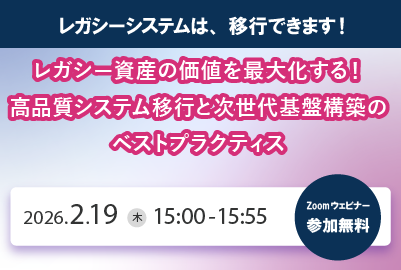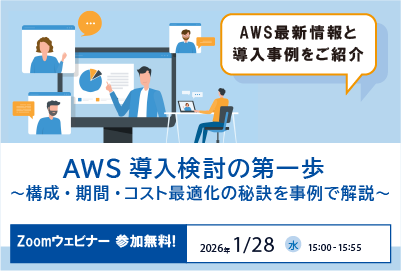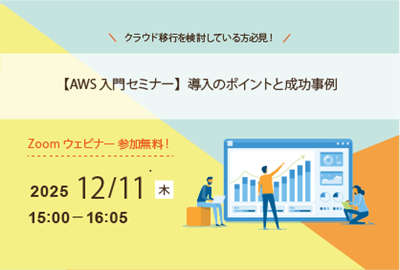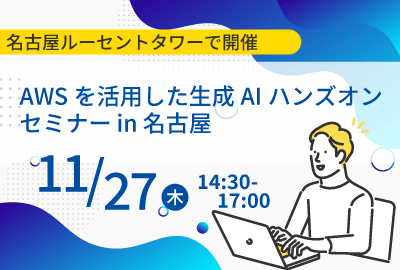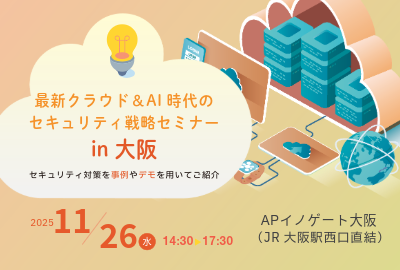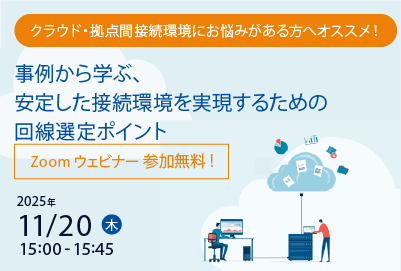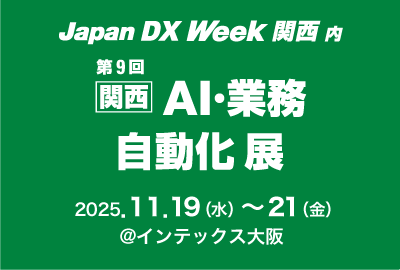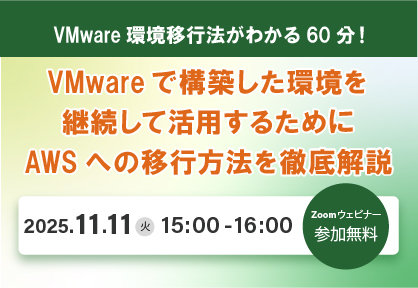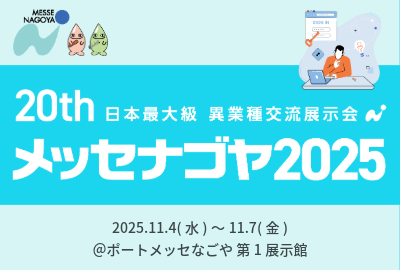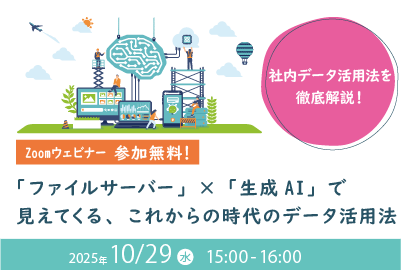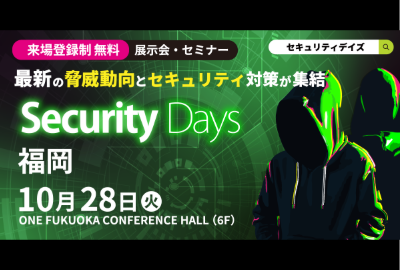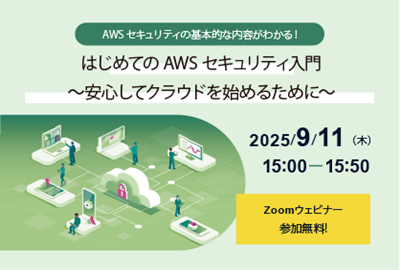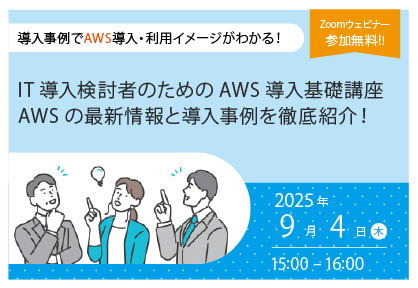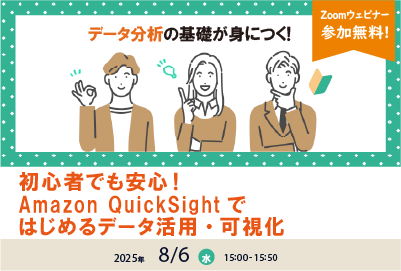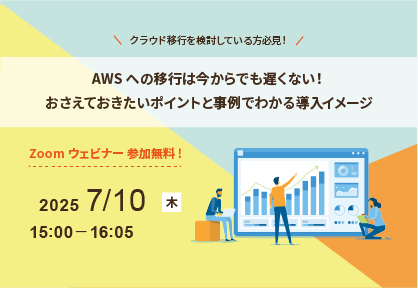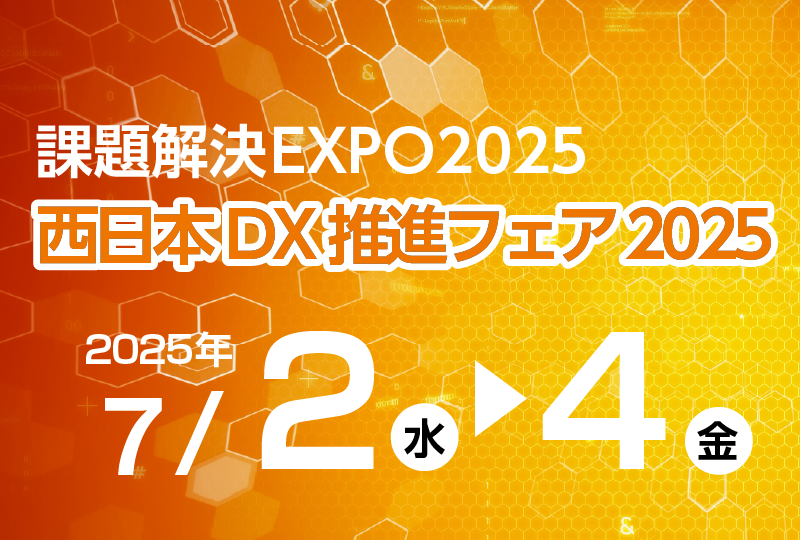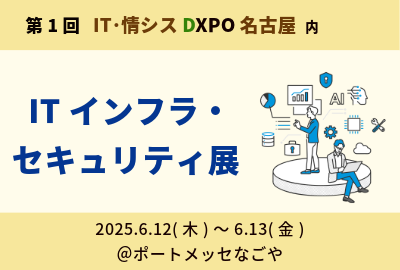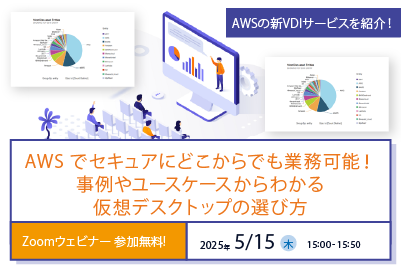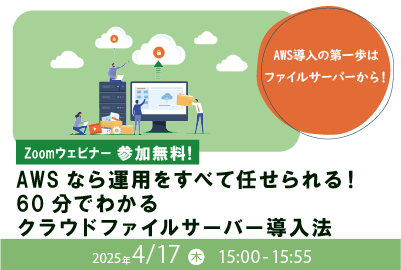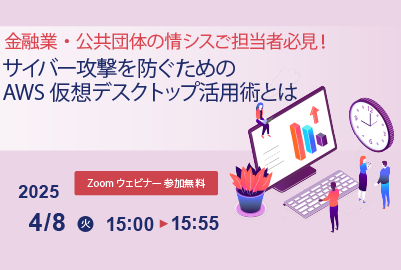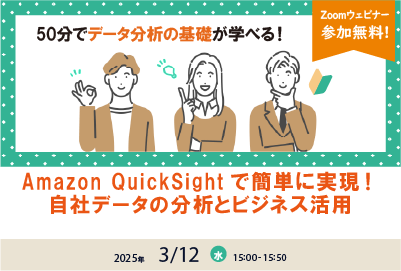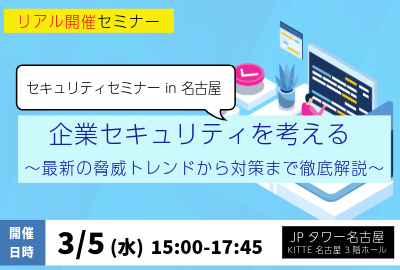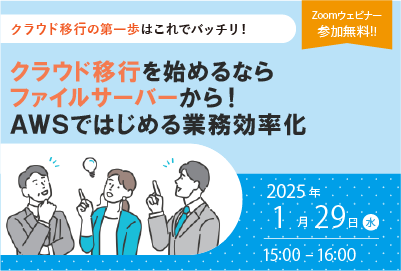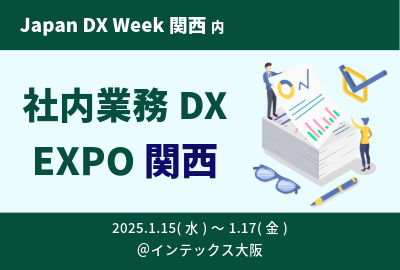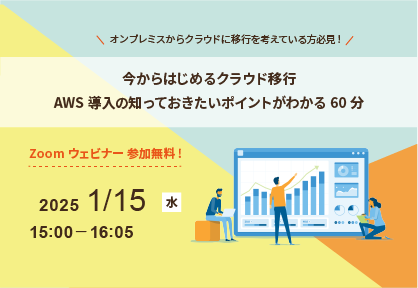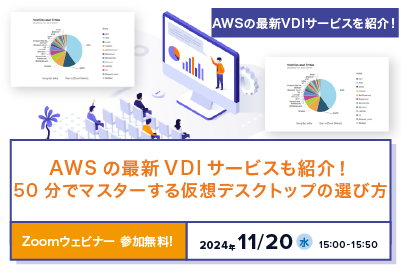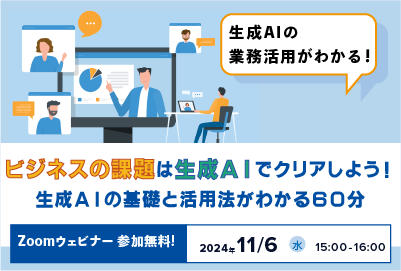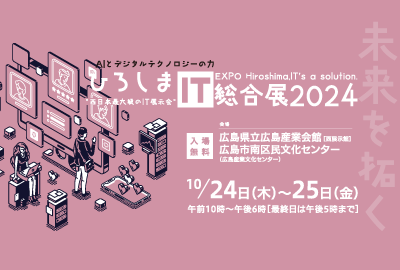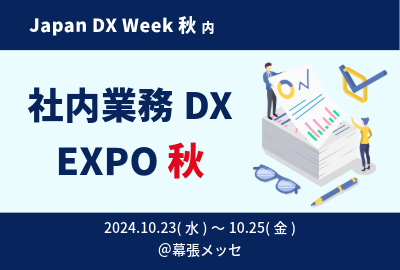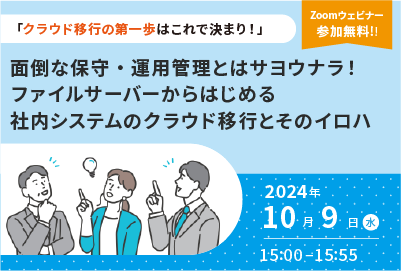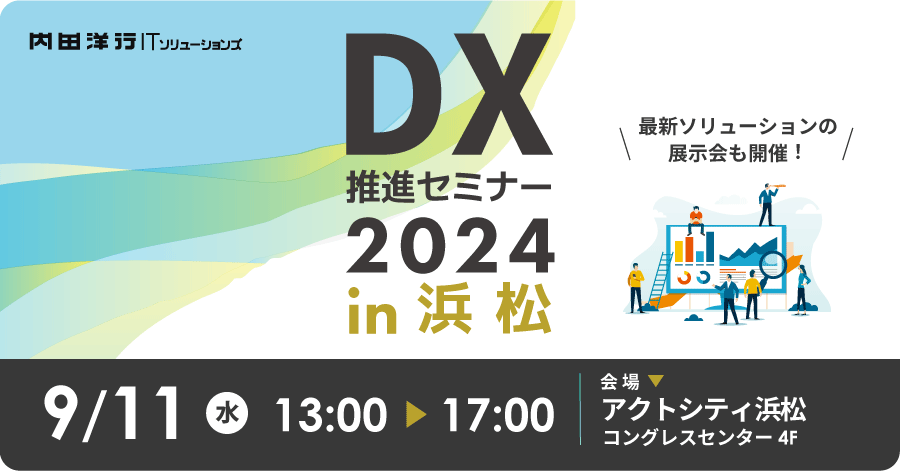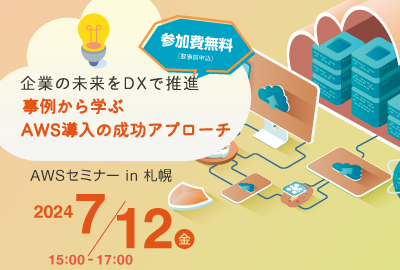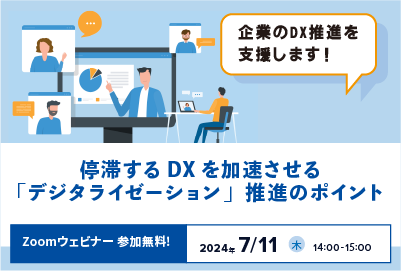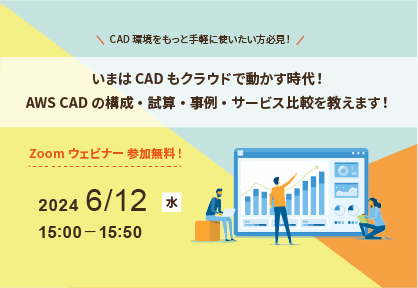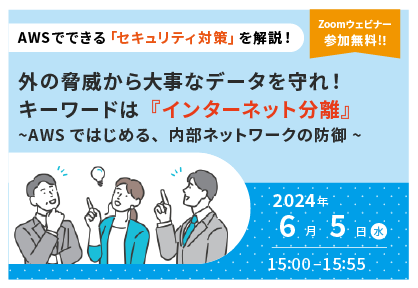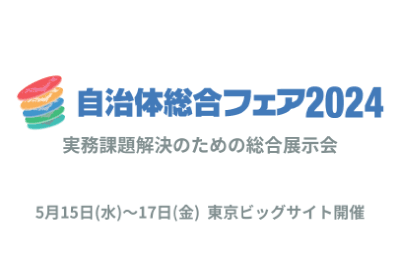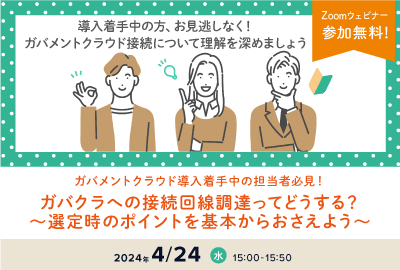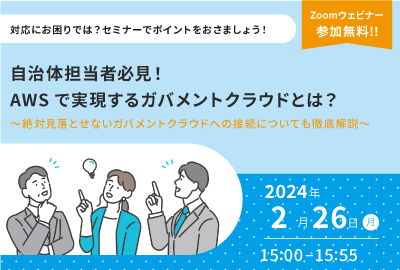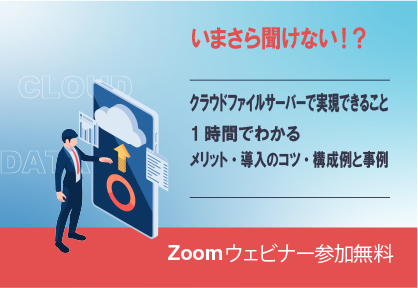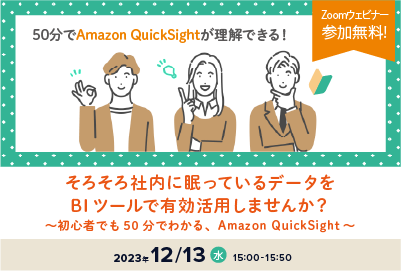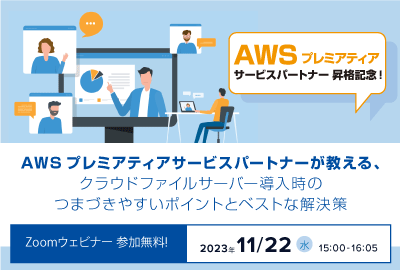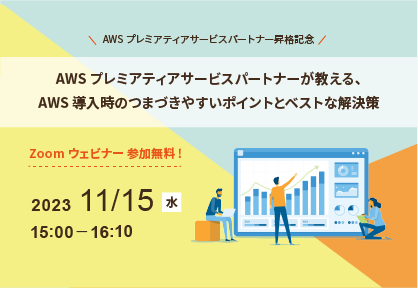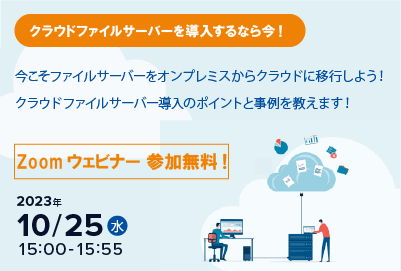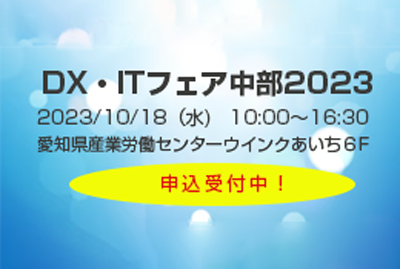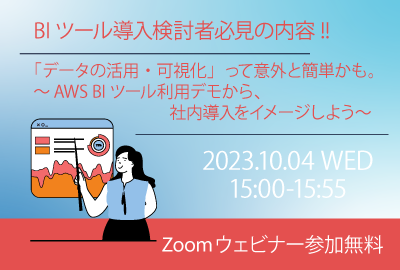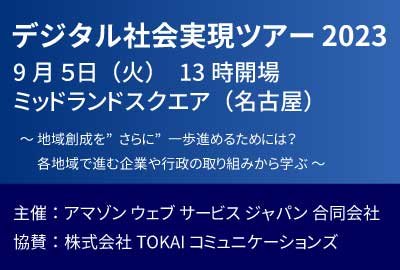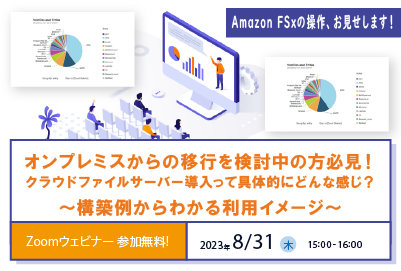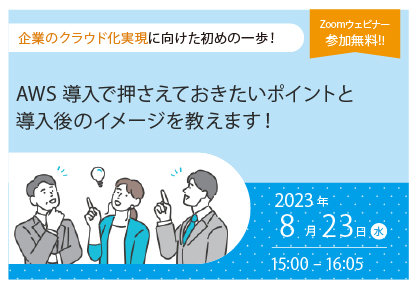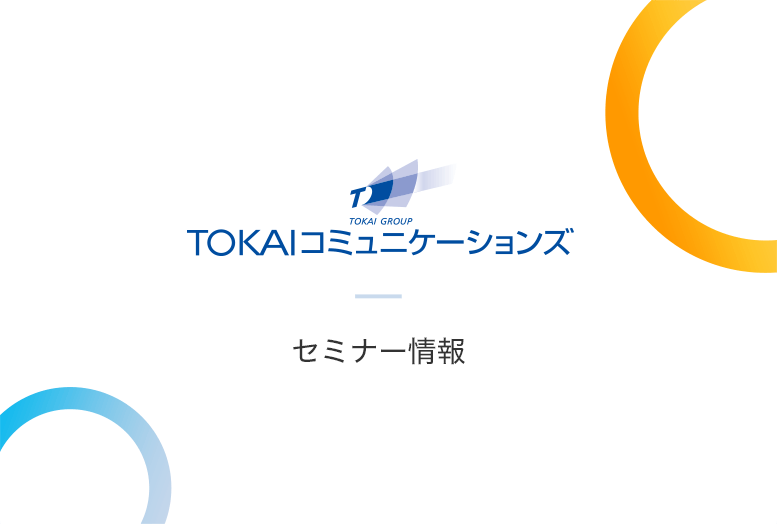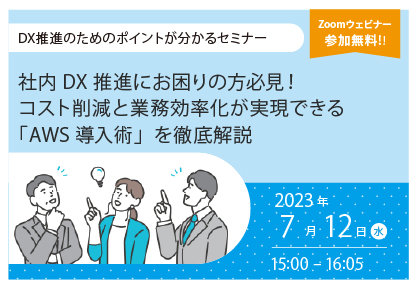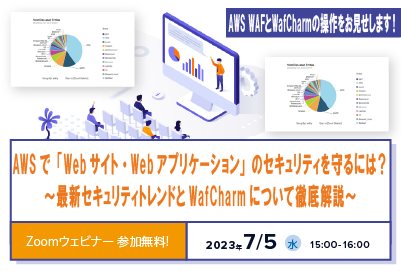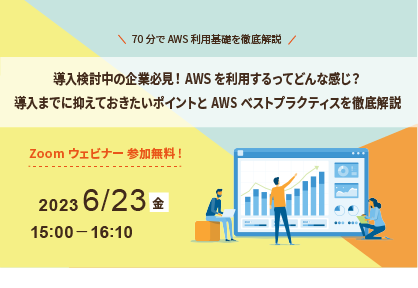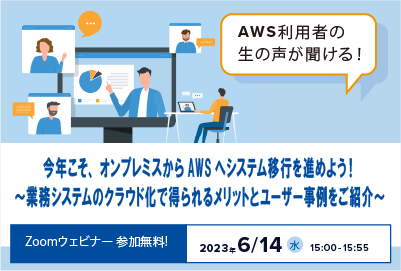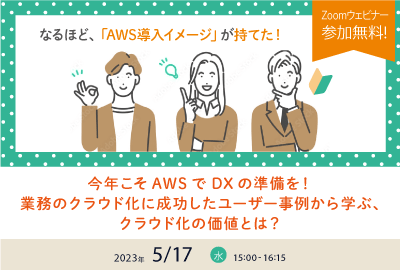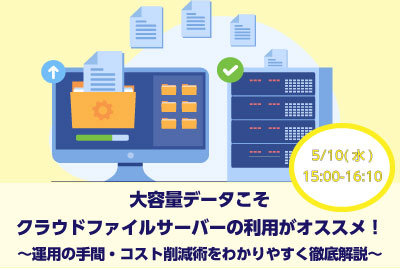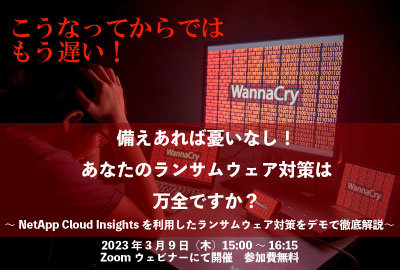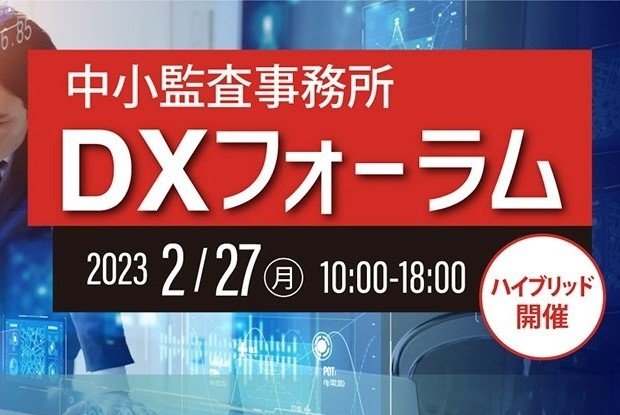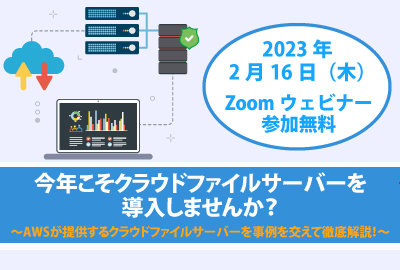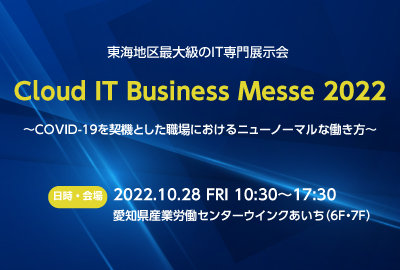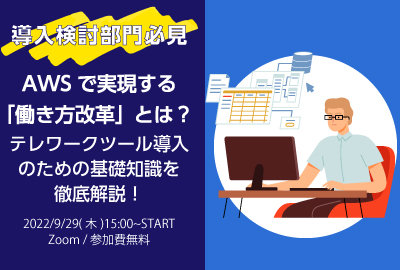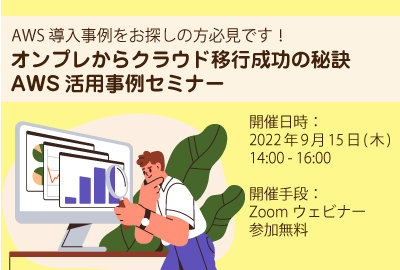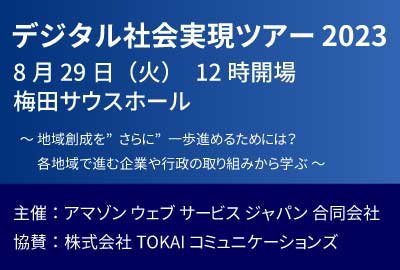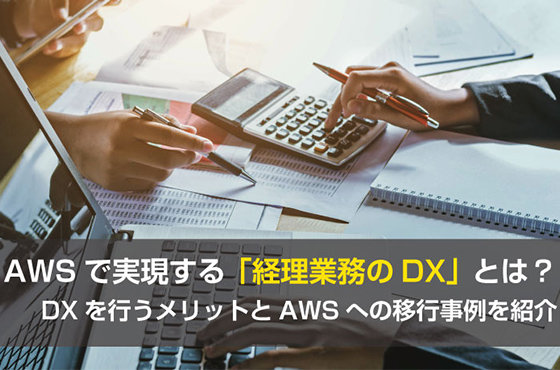
近年、DXの機運が高まってきていますが「バックオフィスのDX」はまだまだ進んでいないのが現状です。バックオフィスのDXは、企業にとって大きな効果があります。今回の記事では、経理部門がDXを行うべき理由、経理業務システムをオンプレミスからAWS環境へ移行した事例をご紹介します。
目次
経理部門がDXを行う意味
まずバックオフィスである経理部門が、なぜDXを進めるべきなのかについて解説します。
軽視されがちなバックオフィス
バックオフィスは、企業にとって重要な役割を担っています。フロント部門が業務に集中するためには、バックオフィスの存在が欠かせません。
そして今、経理部門に求められているのがDXです。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、「デジタル技術を活用して業務プロセスを改善し、会社のビジネスモデルや企業風土を変革させること」を指します。経理部門のDX推進で企業が得られるメリットは、業務効率化、データ分析の精度向上、経営判断の迅速化などが挙げられます。
なぜ今経理部門がDXを行うべきか
ではなぜ、今こそ経理部門がDXを推進するべきなのでしょうか。その理由は、3点あります。
電子帳簿保存法改正
2022年1月に改正された電子帳簿保存法では、電子取引において電子データの保存が義務付けられました。2024年1月からは、請求書・領収書・契約書などの電子データを送受信した場合、電子帳簿保存法が定める要件で保存しなければなりません。経理関連の膨大なデータは、電子帳簿保存法の対象となっているため、経理部門のDX化が急務となっています。
インボイス制度
インボイス制度とは、売り手が買い手に対して、正確な消費税額やその他の情報を記載した「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書の発行を義務付ける制度です。2023年10月よりスタートするため、インボイス制度に対応できる経理業務のDX化が企業に求められています。
2025年の崖問題
2025年の崖問題とは、日本企業が抱える課題(IT人材不足、システムの老朽化、既存システムのブラックボックス化など)が解消できずにDXを実現できない場合、2025年以降最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるといわれています。この問題は、経済産業省発行の「DXレポート 」内で詳細に指摘されており、企業の早急なDX化を推進しています。
経理部門がもたらす経営へのメリット
続いて、経理部門がDXを行った場合、企業経営へのメリットをご紹介します。
金銭的コストおよび人的コストの削減
経理部門には、仕訳や帳簿記帳などの定型業務があります。これらの業務をDXで効率化することで、毎月の工数が大幅に削減できます。空いたリソース(人材や資金)は、ほかの業務へ充当でき、企業成長へとつなげられます。
またペーパーレス化も実現できるため、印刷代・用紙代・プリンターのレンタル費などのコストを大幅に削減でき、ファイリング人員や保管場所の削減にもつながります。
属人化の解消
経理部門には、ベテランスタッフの経験や知識で成り立つ業務があります。この影響から、請求書発行や給与計算・決算業務などのバックオフィス業務は複雑化し、属人化に陥りやすい傾向にあります。
DXの一環として会計システムなどを導入すれば、煩雑な経理業務がルーティン化でき、業務の処理スピードも向上します。会計ソフトは誰でも利用できるため、業務の属人化が解消でき、誰でも同じ結果を出せることが大きなメリットです。
ヒューマンエラーの削減
人力に頼った処理はヒューマンエラーが起きやすく、再発防止策を実施するにしても新たなリソースが必要となり、社員の負担が大きくなりがちです。DXは、この問題の解決にもつながります。
例えば、経費精算時によく起こりがちなのが、提出された書類の不備により差し戻しが発生し、余計な手間がかかるという問題です。入力内容に不備があるとき、それを自動的に検知するシステムがあれば、差し戻しを事前に防ぐことができます。申請者が書類提出前に自ら不備に気づけるため、経理担当者の負担が軽減できます。また、入力ミスが起きやすい転記作業も、自動化できれば大きく効率が改善されるでしょう。
このようにDXを推進することで、経理業務の効率改善が実現できます。これにより、さまざまリソースに余裕が生まれ、生産性向上の施策を打てるようになり、競争優位性の獲得にもつながるのです。
TOKAIコミュニケーションズでは奉行シリーズのAWS移行もサポート
最後に、TOKAIコミュニケーションズが提供している、AWS移行サポートについて紹介します。
奉行シリーズのクラウド(AWS)移行について
現在「勘定奉行シリーズ」を利用している企業のなかでも、クラウド移行を検討している企業は少なくないでしょう。AWSに移行した場合、オンプレミス環境と同じ操作性を保ちながら、サーバー運用・保守のコスト削減ができます。また、セキュリティや拡張性の向上も実現できます。さらに、場所を問わない利用も可能となるため、本格的なDX実現の足がかりとなってくれるでしょう。
TOKAIコミュニケーションズでは、「勘定奉行シリーズ」のAWS移行もサポートしています。AWS環境の構築実績が豊富でAWSアドバンストティアサービスパートナーでもある当社が、「勘定奉行」のAWS環境構築から運用・保守まで、ワンストップでお引き受けしています。
奉行シリーズをAWSに移行した導入事例(永峰・三島会計事務所様)
会計業務の専門家である永峰・三島会計事務所様は、国際監査基準(ISAE3402)の取得を目指すなかで、ITも含めた業務環境の整備が必要となりました。従来、勘定奉行・償却奉行・給与奉行の各奉行シリーズを物理サーバで運用していましたが、スタッフ20名規模の時に構築したシステムを継ぎ足して使用している状態で、セキュリティやバックアップ体制の抜本的な見直しが急務でした。
AWS移行を検討する中で抱えていた課題は、次のようなものでした。
- 物理サーバ環境でのバックアップやログ管理体制の不備
- 国際監査基準取得に必要なセキュアな情報基盤の構築
- 約60名のスタッフが一斉にアクセスする業務システムの安定稼働
- IT専門部門を持たない組織での継続的な運用管理
これらの課題を解決すべく、TOKAIコミュニケーションズがパートナーとして選ばれました。同事務所では4社のITベンダーを候補に挙げ、その中から「AWSと奉行シリーズの豊富な知見」「士業での実績」「適正なコスト」を評価してTOKAIコミュニケーションズを選定。奉行シリーズ一式のAWS移行プロジェクトは2016年夏にスタートし、2017年5月末に無事カットオーバーを迎えました。
奉行シリーズをAWSに移行したことで、オンプレミス環境と同じ操作性を保ちながら、次のような効果を実現しました。まず、データの自動バックアップとアクセスログの取得により、万一の障害時やインシデント発生時のリスクに対応できる体制が整いました。また、AWSへの専用回線とセキュアなネットワーク環境により、外部からも安全にシステムにアクセスできるようになりました。さらに、TOKAIコミュニケーションズのサポートデスクによる運用サポートにより、IT専門部門を持たない同事務所でも安心してシステムを利用できる環境が整いました。
同事務所の松尾氏は、「メールで問い合わせをすると、まず電話で連絡をいただき、その後メールでも返信があります。困っている時は一刻も早く問題を解決したいので、迅速な対応は非常に安心感があります」と、AWS移行後のサポート体制を高く評価されています。
永峰・三島会計事務所様の奉行シリーズAWS移行プロジェクトについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
AWS導入事例 | 永峰・三島会計事務所様(専門サービス業)
まとめ
経理部門をはじめとしたバックオフィス業務のDX化は、めぐりめぐって企業に大きな利益をもたらします。この機会に、オンプレミス環境からAWS環境への移行を検討してみてはいかがでしょうか。なお、TOKAIコミュニケーションズでは「勘定奉行」などをオンプレミス環境からAWS環境へ移行するワンストップサポート「AWSマイグレーションサービス」も提供しています。ご興味がある方は、お気軽にご相談 ください。
関連サービス
おすすめ記事
-
2024.03.29
障害に強いプライベートネットワークを構築しよう|Amazon VPCとAmazon Direct Connectを使った冗長構成について解説

-
2023.04.11
プライベートネットワークをクラウド上で構築しよう! クラウドのメリットとAmazon VPCについて解説

-
2022.03.28
AWS Transit Gatewayを導入するメリットとは?構造や構築例を詳しく紹介

-
2021.08.30
企業がクラウド利用時に検討すべきネットワークの課題とは?

-
2020.04.27
AWS Direct Connectとは、Direct Connectの活用事例